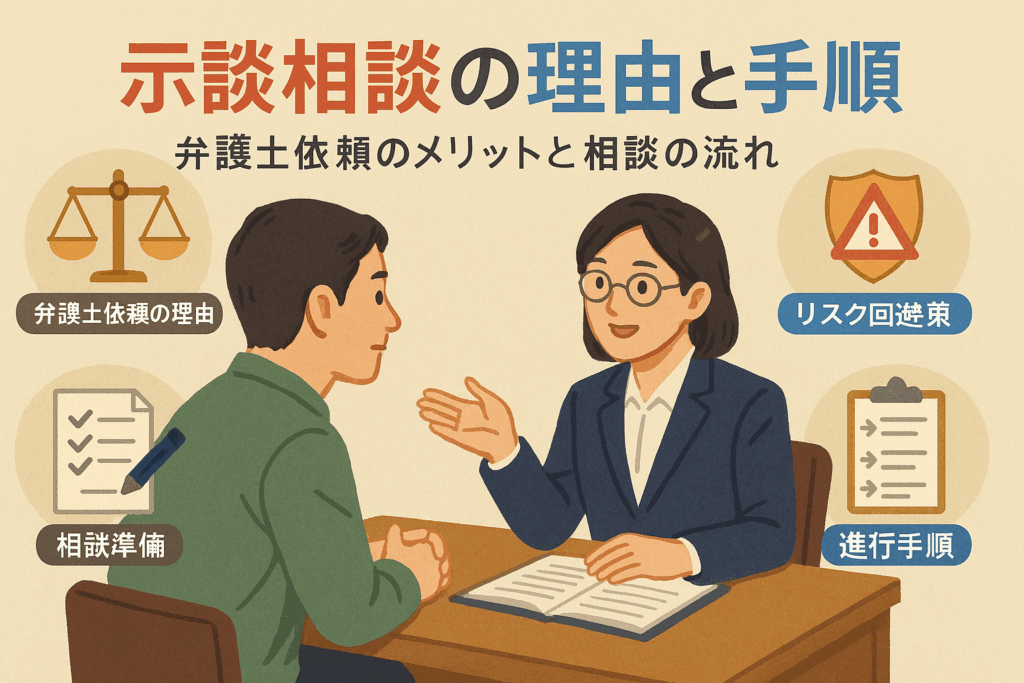「保険会社からの提示額は、本当に適正なのか?」
交通事故示談で、「もっと賠償金を受け取れるはずだった」と後悔する方は珍しくありません。例えば、弁護士に相談した場合としなかった場合とで、慰謝料が2倍以上違う事例も数多く報告されています。被害者が自分で示談交渉を進めた場合、弁護士基準(いわゆる裁判所基準)での算定が採用されず、数十万円〜数百万円もの金額差が生じるケースもあります。
また、後遺障害認定や過失割合で争いになった際、弁護士の有無は示談成立のスピードや精神的負担、手続きの精度に大きく影響します。「想定外の費用や長期化が怖い」「示談で必要な書類や進め方がわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
法律知識や豊富な交渉経験を持つ専門家がサポートすることで、「交渉がスムーズに進み、納得の金額を獲得できた」という声は少なくありません。この記事では、数々の判例や公的データをもとに、依頼すべきケース・リスク・弁護士選びのコツ・費用の実態など、事故被害者が必ず知っておきたいポイントを深掘りしていきます。
示談で損をしたくない方、本当に納得できる結果を目指す方は、まずは事実と成功例を知ることから始めてください。
交通事故の示談で弁護士に依頼するべき理由を深掘り解説する
交通事故の示談で弁護士が必要となる代表的ケース
交通事故において弁護士が必要となる状況は限られていますが、次のようなケースでは特に専門的なサポートが頼りになります。
- 重症や後遺障害が残った場合
治療期間が長引き、後遺障害等級の認定申請が関わる場合は、適切な賠償金・慰謝料を得るために法的知見が不可欠です。
- 過失割合を巡るトラブル
相手方との間で過失割合の調整がつかず、損害賠償額に大きな差が生じるケースでも、弁護士に依頼することで第三者的な立場から的確に主張を行えます。
- 保険会社との示談交渉が難航した場合
弁護士基準をもとに示談金を増額できるなど、大きなメリットがあります。
弁護士依頼なしで示談すると生じやすいリスクと注意点
弁護士を介さずに示談を進める場合、さまざまなリスクを抱えることになります。
-
保険会社の提示金額が相場に比べて低くなることが多い
-
交渉や書類作成の負担が被害者自身にかかる
-
過失割合や後遺障害等級の認定で不利に扱われやすい
特に、示談金が低くなるリスクは無視できません。保険会社は自社基準で賠償額を算定するため、専門知識がないままサインをしてしまうと、本来受け取れるべき慰謝料に届かないことが多くあります。また、交渉過程で精神的にも大きな負担がかかるため、注意が必要です。
弁護士に依頼して後悔しないための心得と事前確認ポイント
弁護士に依頼した後に「思ったより費用が高かった」「連絡が遅い」といった後悔をしないためには、事前の確認が不可欠です。
-
費用の明確な説明を求める(着手金、報酬金、実費など)
-
弁護士特約の有無を保険会社に確認し、利用有無を把握する
-
過去の解決事例や実績をチェックする
-
契約前に相談の流れや対応体制を事前に確認する
特に弁護士特約が付帯されていれば、多くの場合自己負担ゼロで相談・依頼が可能です。契約や進行状況の説明が丁寧で、メールや電話での連絡が迅速な事務所を選ぶことも大切です。
示談交渉に強い弁護士の選定基準とランキング活用法
示談交渉に強い弁護士を選ぶには、以下のようなポイントを比較検討するのが有効です。
| 選定基準 | 確認ポイント |
|---|---|
| 専門性・実績 | 交通事故・示談解決実績、最新の解決事例 |
| 費用・相談体制 | 明瞭な料金体系、無料相談可能か |
| 地域密着度 | 事故現場や通院先に近い事務所、対応範囲 |
| 依頼者の口コミ・評判 | 他の利用者の評価や感想の良さ |
ランキングや事務所の比較サイトも参考になりますが、一律ではなく、自分のケースや地域、希望する対応内容に合わせて選ぶことが重要です。実際の面談や電話相談で信頼できるかどうか、得意分野や報酬体系についても直接確認しましょう。
示談交渉の具体的な流れと弁護士介入の最適タイミング
事故発生から治療・後遺障害認定までの基本フロー
交通事故が発生した場合、まず重要なのは速やかな救護と警察への通報です。その後は医療機関で適切な治療を受け、症状固定まで通院します。治療が終わったら、後遺障害が残る場合には所定の診断書をもとに後遺障害等級認定の手続きを行う必要があります。ポイントは、事故直後から治療記録をしっかり残すことと、保険会社への報告を怠らないことです。
-
事故発生・警察へ通報
-
医療機関での治療
-
治療終了後、後遺障害等級認定
-
示談交渉開始
治療内容や等級認定はその後の示談交渉や慰謝料に大きく影響します。書類や診断書の保管も大切です。
示談交渉開始から成立までの詳細プロセス
示談交渉は、主に保険会社との書類のやり取りと損害賠償額の提示からスタートします。ここで重要なのは、保険会社からの提示額が「弁護士基準」より低いことが多い点です。書類整備が不十分だと交渉が難航するため注意しましょう。
| 流れ | 主な対応内容 |
|---|---|
| 損害額・証拠書類の準備 | 医療費明細、診断書、休業損害明細など |
| 保険会社へ請求書提出 | 必要書類を揃え速やかに提出 |
| 損害賠償額の提示・交渉 | 金額や過失割合の調整 |
| 最終合意・示談書の作成 | 双方合意後、正式な書面を交わす |
複雑な場合や過失割合で争いがあるときは、早期に弁護士へ相談しましょう。
弁護士介入が遅いと感じる理由と対応策
弁護士に依頼しても進行が遅いと感じる主な理由は、証拠収集や書類のやり取り、保険会社との交渉が想定以上に時間を要するためです。また、後遺障害等級認定や医療機関との連携も影響します。こうした事態を避けるため、下記の対策を意識しましょう。
-
書類は早めに提出し、不備があれば即座に対応
-
進捗に疑問があれば、弁護士にこまめに連絡・確認
-
依頼内容や目標金額を明確に伝える
スムーズな進行のためには、早期の準備と積極的なコミュニケーションがカギです。
示談成立に必要な法的・実務的書類と準備事項
示談成立の際には、正確な損害賠償額を裏付ける書類と、示談書作成が不可欠です。特に重要となる主な書類は次の通りです。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 示談書 | 双方の合意内容を明記した正式書類 |
| 医療費・治療費明細 | 正確な治療や通院費の証拠 |
| 休業損害証明書 | 休業による損害が生じた場合に必要 |
| 後遺障害等級認定証明書 | 等級が認定された場合 |
書類整備は担当弁護士や保険会社とよく相談し、原本や控えを確実に保管してください。持参や郵送前には記載漏れがないか再確認することも大切です。
交通事故の示談で弁護士に依頼するメリットと費用・デメリットの透明解説
弁護士介入で期待できる示談金増額の根拠と事例紹介
交通事故の示談金は、被害者自身だけで交渉する場合と、弁護士が介入する場合で大きく異なることが多いです。一般的に加害者側の保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算しますが、弁護士が関与すると「弁護士基準」(裁判所基準)が適用され、慰謝料や損害賠償金が増額するケースが目立ちます。
例えば、むち打ち症で通院半年の場合、保険会社提示だと総賠償金が約50万円に対し、弁護士介入で基準を適用すると100万円を超える例もあります。
増額のポイント
-
後遺障害等級の適正認定
-
損害額の根拠資料提示
-
裁判所基準の主張徹底
多くの依頼者が保険会社との金額差に納得し、示談金アップを実現しています。
弁護士費用の詳細と弁護士特約利用時の仕組みや注意点
弁護士への依頼費用は通常「着手金」「報酬金」「実費」などで構成されます。着手金は依頼時に支払うもので、報酬金は示談や判決で得た金額に連動する成果報酬制が一般的です。
弁護士費用(おおよその一例)
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 着手時に発生。0~10万円前後が多い |
| 報酬金 | 成功報酬。獲得額の10~20%程度 |
| 実費 | 書類取得・郵便・交通費等 |
自動車保険に「弁護士特約」が付帯されていれば、弁護士への相談や依頼にかかる費用が保険会社から支払われるため、多くの方が負担なく専門家に依頼できます。
注意点
-
保険会社指定の範囲や限度額を必ず確認
-
特約を使うことで保険等級が下がることはありません
-
もらい事故など場合により利用制限があるケースもあります
弁護士費用倒れや長引くリスクの現実的な対処法
「弁護士費用倒れ」とは、弁護士にかかる費用が示談金増額分を上回ってしまう状態を指します。これを防ぐためには、相談時に費用と交渉見込額のバランスを事前確認することが重要です。多くの事務所で無料相談が可能なため、納得できる見積もりを取り、後悔しない判断が可能です。
また、示談交渉が長引くことで精神的・金銭的負担が増すケースもあります。進捗が遅いと感じた時には、
-
進捗状況の定期的な確認
-
解決までの目安期間を確認
-
他の弁護士事務所にも相談し比較する
こうした行動がリスクの最小化につながります。
依頼前に知っておくべきメリット・デメリットの全容
弁護士を利用する最大のメリットは、適正な慰謝料・損害賠償金の獲得と、保険会社との煩雑な交渉や手続き全般の代行です。専門家の知識と経験により後悔や損失リスクが大幅に減ります。
一方、デメリットとして
-
費用倒れの可能性(特に軽微事故や過失割合が大きい場合)
-
解決までに時間がかかる場合がある
-
稀に意思疎通が取りづらいと感じる場合も
といった点が挙げられます。
以下のような場合に、弁護士依頼が強く推奨されます。
-
保険会社提示の金額に納得できない
-
後遺障害認定を受けたい
-
10対0など過失割合でもめている
-
弁護士特約がある
事前に費用や見通しを確認し、自身に合った進め方を選択しましょう。
弁護士の選び方・ランキング・口コミ比較で失敗しない依頼先決定
主要弁護士法人の特色・対応エリアと専門分野の違い
弁護士法人ごとに規模や得意とする分野、対応エリアには特徴があります。全国展開している大手法人は、交通事故分野でも豊富な実績や交渉ノウハウが蓄積されています。一方で地域密着型事務所は、地元の医療機関や保険会社との連携を強みとしており、迅速な対応が期待できます。
下記のテーブルは、弁護士法人の主な違いを比較したものです。
| 法人名 | 対応エリア | 主な強み | 専門分野 |
|---|---|---|---|
| 全国型大手 | 全国 | 実績豊富・交渉力が強い | 交通事故・医療事故・労災 |
| 地域密着型事務所 | 地域限定 | 地域特化・迅速な面談対応 | 交通事故・相続 |
| オンライン対応型 | 全国 | オンライン面談・柔軟な対応 | 交通事故 |
利用者の口コミと評判から見えるメリット・注意点
利用者の口コミには、実際に弁護士に依頼した際の対応力や解決のスピード、説明の分かりやすさなどが反映されています。特に多かった評価ポイントをリストにまとめます。
-
親切で丁寧な説明をしてくれた
-
対応が迅速だった
-
示談金が大幅に増額した
-
連絡が遅い場合があった
一方で注意点としては、
-
事前説明が十分でなかった
-
期待したより期間が長引いた
-
費用面の説明が分かりにくかった
といった声も確認されています。
口コミは実際の体験に即している分、参考になりますが、個人差もあるため複数の評判を比較検討することが大切です。
相談窓口・対応スピード・オンライン対応などの利便性比較
弁護士事務所の利便性は、相談窓口の多さや受付体制、初動対応の早さによって大きく異なります。電話・メール・LINEなど、複数のチャネルで相談可能な事務所は依頼しやすい傾向にあります。
サービスの利便性比較表を参考にしてください。
| 相談方法 | 対応時間 | 相談のしやすさ |
|---|---|---|
| 電話 | 平日・休日対応 | 即時性が高い |
| メール | 24時間受付 | 文章で詳細に相談できる |
| LINE | 24時間受付 | 気軽に相談・写真送信も可 |
| オンライン面談 | 予約制 | 自宅から全国どこでも対応 |
オンライン相談や休日・夜間対応を行っている事務所は、仕事が忙しい方や遠方の方にも最適です。
弁護士ランキングの選出基準と信頼できる情報の見きわめ方
事故に強い弁護士ランキングは複数存在しますが、選出基準を確認することが重要です。主な基準として多く挙げられているものを示します。
-
解決実績や取扱件数
-
専門性(交通事故特化・専門チーム設置など)
-
口コミ評価や満足度
-
費用やサポート体制の明確さ
ランキング情報を閲覧する際は、掲載事務所の公式ページの実績や弁護士費用、対応エリアや口コミ内容などもあわせて確認しましょう。信頼できるランキングは、根拠やデータを明示していることが多いのも特徴です。信頼性や透明性の高い情報だけを根拠に選ぶことが、依頼先選定で失敗しない最大のポイントです。
示談金の請求可能額・相場・内訳詳細と交渉成功のポイント
示談金の主な構成要素とそれぞれの計算方法
交通事故の示談金は主に「治療費」「慰謝料」「休業損害」「後遺障害逸失利益」などで構成されます。慰謝料の計算方法は通院日数や治療期間などをもとに算定され、後遺障害等級が認定された場合は等級ごとに金額が異なります。休業損害は事故による就労不能日数と収入をもとに計算され、逸失利益は将来得られると見込まれる収入から事故により減少する分を割り出します。保険会社は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のいずれかで算定しますが、専門家が介入することで最も高額となる弁護士基準が適用されやすくなります。
| 構成要素 | 概要 | 計算のポイント |
|---|---|---|
| 治療費 | 医療機関への実費 | 領収書や診断書の確保が重要 |
| 慰謝料 | 精神的損害への補償 | 通院日数や治療期間を基準 |
| 休業損害 | 仕事を休んだことによる損失 | 給与明細・収入証明が証拠となる |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺症が残った場合の減収分 | 等級認定と年収・労働能力喪失率で算出 |
10対0事故や過失割合特殊ケースの示談金相場例
10対0事故の場合、過失ゼロ側は原則保険会社を介さずに相手方に賠償請求を行います。このケースでは交渉力が重要で、示談金の相場は事故状況や怪我の程度によって大きく変動します。例えば、軽傷で通院2か月程度の場合の慰謝料は約20~40万円程度、後遺障害認定がされた場合は逸失利益を含め合計100万円以上になることもあります。過失割合が9対1や8対2など特殊ケースでは、提示額が不当に低く設定されることが少なくありません。こうした時は基準ごとの相場や増額交渉ポイントを把握しておくことが大切です。
| ケース | 一般的な慰謝料相場(目安) | メモ |
|---|---|---|
| 10対0(通院のみ) | 20~40万円 | 自分で交渉必要 |
| 9対1(軽傷) | 10~30万円 | 過失修正に注意 |
| 後遺障害あり | 100万円以上 | 等級・年収が影響 |
示談金増額交渉で陥りやすい落とし穴と回避策
示談金増額を目指す際、保険会社から「基準額はこれが限度」と説明されることがあります。しかし妥協することなく、弁護士基準での査定を求めることが大切です。交渉に慣れていない場合、証拠資料の不備や、不十分な主張により本来の賠償金を得られないリスクが生じます。主な回避策は以下の通りです。
-
事故直後から診断書や領収書など証拠を管理する
-
過失割合や慰謝料相場を事前に確認しておく
-
交渉内容は必ず文書でやり取りする
-
状況に応じて弁護士や専門家に相談し、第三者の目で判断する
これらを徹底することで、示談金の不利益や後悔を防ぎ確実な交渉につなげることができます。
最新の示談金事例紹介と公的データによる透明性担保
近年は後遺障害等級認定を受けた場合の示談金増額例や、重篤事故による高額賠償が注目されています。公的な事故統計や判例データを活用することで、自分と似た状況の相場を把握しやすくなります。たとえば裁判例では、弁護士が介入した結果、当初提示額の2~3倍まで増額されたケースも報告されています。また、交通事故相談センターなどの定期発表や自治体の事故相談窓口でも、主要な示談金実例が公開されています。
| 年度 | 後遺障害等級 | 増額前提示額 | 弁護士介入後 | 増額幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最新 | 14級 | 65万円 | 120万円 | 55万円増 |
| 最新 | 12級 | 210万円 | 390万円 | 180万円増 |
| 最新 | 非該当 | 30万円 | 40万円 | 10万円増 |
相場や事例を参考に、現状を正確に理解しておくことが、自身の納得と将来のトラブル回避につながります。
示談交渉でもめやすいポイントとトラブル回避・解決法
示談でよく問題となる8つのもめやすいパターン詳細解説
交通事故の示談交渉では、被害者と加害者の間で特に以下の8つのパターンがもめやすい傾向にあります。
- 過失割合の主張に差がある場合
- 治療費や通院日数の妥当性を巡る争い
- 慰謝料や損害賠償金額の提示差異
- 後遺障害等級認定の有無や程度での対立
- 示談書の内容に関する認識のズレ
- 保険会社による一方的な示談提案
- 休業損害や逸失利益など特別損害の算定方法
- 加害者が個人で任意保険非加入の場合の対応
上記のトラブルを未然に防ぐには、弁護士に早めに相談し専門的知見を活用することが重要です。書類や証拠を整理しておくことで、交渉が円滑になりトラブルを回避できます。
示談不成立時の法的対応と時効・期間管理の重要性
示談交渉がまとまらない場合、次の法的手段を選択できます。
| 法的手段 | 特徴・ポイント |
|---|---|
| 民事調停 | 裁判所で第三者の調整を受けながら和解を目指す。 |
| 訴訟提起 | 法廷で法的主張を行い、最終的な判断を求める。 |
| あっせん・仲裁 | 中立機関により早期解決を図る方法。 |
傷害や損害賠償の請求には時効(通常3年)があり、加害者側や保険会社との示談交渉が長引いた場合でも請求期限に注意が必要です。交渉が長期化する場合には、時効の中断措置(催告・訴訟提起など)も検討しましょう。
保険会社や加害者側との連絡不備時の対処方法
保険会社や加害者側からの連絡がない、あるいは連絡が途絶えがちな場合は、以下の手順を意識して対処すると効果的です。
-
交渉内容や経緯を時系列で記録・ファイリング
-
証拠となる郵便やメール、LINEの履歴保存
-
書面による問い合わせや催告を検討
-
専門家(弁護士)への早期連絡・相談
特に重要な書類(診断書、領収証、事故証明書など)はきちんと整理し、トラブル防止・リスク最小化に努めましょう。
加害者側弁護士が登場した際の被害者の対応ポイント
加害者側から弁護士が出てきた場合、被害者として冷静に対応することが何より大切です。
-
無理な合意や署名を急がない
-
交渉記録を必ず保管する
-
一方的な条件提示には納得できるまで説明を求める
-
自身も早急に弁護士へ相談し、専門家同士での交渉とする
-
相手弁護士の主張や示談条件は、弁護士経由で内容確認・検討
専門家が介入することで、公平な基準や示談額が適正となりやすくなります。不安や疑問が生じた場合は、早めに信頼できる弁護士へ相談することが大切です。
弁護士特約の正しい理解と効果的な活用法・注意点
弁護士特約の概要と対象となる事故の条件
自動車保険の弁護士特約は、交通事故の被害者となった際、示談交渉や損害賠償請求などを弁護士に依頼した場合の費用をカバーする保険です。主な対象は人身事故や物損事故の被害者で、相手方への請求手続や話し合いに利用できます。加害者への明確な責任が求められるため、10対0のもらい事故や相手方が任意保険未加入の場合にも活用可能です。ただし、契約内容によっては適用範囲や金額上限、使えないケース(加害者側・自損事故など)があるため、事前に保険証券や約款を確認しておくことが大切です。
弁護士特約利用時の手続きの流れとポイント
弁護士特約を利用する際は、まず保険会社へ利用希望を連絡します。次に、示談交渉や賠償請求の内容・状況を整理し、相談が必要な弁護士事務所を選定します。その後、必要書類(事故証明、診断書、保険証券など)を準備し、弁護士と面談して委任契約を結びます。保険会社の承認を得て費用の支払いが進むため、弁護士費用の見積もりや条件を事前に確認することが重要です。
下記に特約利用時の主な流れをまとめます。
| 手続きの流れ | ポイント |
|---|---|
| 保険会社に連絡 | 利用可否を早期確認 |
| 必要書類の収集 | 事故証明・損害明細など |
| 弁護士選び・相談 | 実績や対応エリアを比較 |
| 弁護士と契約 | 委任契約締結・費用見積もり |
| 保険会社への請求 | 窓口や申請方法を確認 |
申請は速やかに行うことで弁護士対応も円滑に進みます。
実際に弁護士特約を使った成功例・失敗例の紹介
弁護士特約を利用したケースでは、相手方との交渉で慰謝料や治療費の増額に成功する例が多くみられます。例えば、当初の保険会社提示額よりも数十万円以上増額に至った事例や、むちうち症状でも後遺障害等級が認定されたことで賠償額が大幅に変わった例などがあります。一方、依頼する弁護士を十分に比較せず、交通事故案件の経験が少ない弁護士に依頼した結果、示談交渉が長期化したり、連絡が滞るケースも報告されています。
主なポイントをリストでご紹介します。
-
成功例
- 慰謝料や休業損害の増額が実現
- 後遺障害等級認定による賠償額の上昇
- 交渉ストレスの軽減
-
失敗例
- 弁護士の対応が遅い、連絡がこない
- 専門性の低い弁護士選びで不満が残る
安心して利用するには、事前の弁護士比較や実績・評判のチェックが重要です。
弁護士特約利用時のデメリットやトラブル事例と回避法
弁護士特約の利用にはメリットが多い一方、注意すべき点も存在します。たとえば、弁護士報酬が特約の上限を超える場合に自己負担が発生する点や、一部の保険会社では特定の弁護士しか選べないなど制約があることがあります。また、申請時の手続きミスや連絡不足によるトラブル、費用倒れになるリスクも懸念されます。
回避法としては、次の対策が有効です。
-
弁護士費用が特約内に収まるか事前確認する
-
特約で自由に弁護士を選べる条件か保険会社に確認する
-
申請手続き・連絡を正確かつ速やかに行う
-
見積もりや契約内容を書面で確認する
このような注意点を押さえることで、弁護士特約を安心して効果的に活用できます。
示談成立までに押さえるべき重要な法律知識と最新動向解説
示談交渉で被害者が知るべき法律の基本知識
交通事故の示談交渉を進める際は、民法や自動車損害賠償保障法の基本的な仕組みを知ることが重要です。特に損害賠償請求では「民法709条(不法行為)」が根拠となり、被害者は加害者に対し事故による損害・慰謝料の賠償を求められます。
また、保険会社との交渉が多いため、任意保険・自賠責保険の違いも押さえておきましょう。示談金は損害項目のひとつずつ適正に計算される必要があり、専門的な知識があると納得のいく条件をつかみやすくなります。
主な基礎知識(抜粋)
-
民法による損害賠償請求権
-
慰謝料の基準(自賠責・任意保険・弁護士基準)
-
保険会社と直接交渉する場合の注意点
後遺障害認定や過失割合算定の法的ルール
後遺障害が残る場合は、認定手続と等級判断が賠償額に大きく影響します。認定申請は主治医の診断書や後遺障害診断書が必要となり、損害保険料率算出機構で等級が決まります。認定等級ごとの賠償金額は異なるので、適正な申請を心がけましょう。
過失割合については、事故の態様ごとに判例の蓄積があり、加害者・被害者の責任割合が調整されます。近年では実務指針も更新されており、不利な割合で交渉が進みそうな際は専門家のチェックが有効です。
主なルールまとめ
-
後遺障害認定は専門性が高い
-
等級別の慰謝料・逸失利益基準に注意
-
過失割合は判例や解説書をもとに修正可能
最新の裁判例・法改正情報の概要と影響
最近の裁判例では、慰謝料や逸失利益の判断基準がより被害者保護にシフトする傾向も出ています。法改正による損害賠償額の算定方法や、保険商品の内容更新、時効期間の見直しなど、実務に直結する変化もみられます。
表:近年の主な動向
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 傷害慰謝料 | 弁護士基準見直し(増額事例が増加) |
| 損害算定基準 | 一部の損害項目で細分化・明確化 |
| 手続き・時効 | 原則3年(例外もあり) |
変化の影響を見逃さないことで、交渉の際に有利な材料が得られる場合があります。
示談交渉時に知っておくべき契約法のポイント
示談を成立させる際は、示談書の文言が非常に重要です。曖昧な表現や必要な条項の抜け落ちがあると、後々トラブルになるケースも多く見受けられます。示談書には「賠償項目」「今後の請求権放棄」「支払い時期」など具体的な内容の明記が求められます。
必ず押さえておきたいポイント
-
全損害項目の明確な記載
-
支払い方法・時期の特定
-
将来の損害(後遺障害等)も踏まえて条項を調整
-
不明点や不安点は弁護士等に確認
示談交渉においては多角的な法律知識が結果を左右します。書類のチェックや条項の見落としがないか、慎重に手続きを進めましょう。