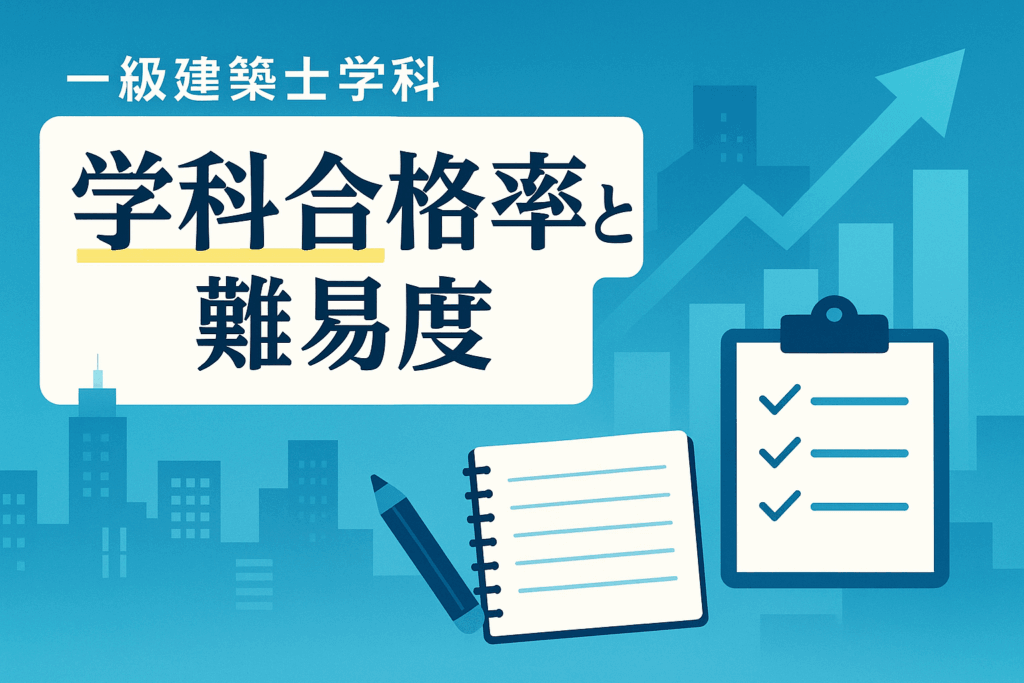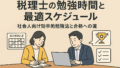一級建築士学科試験の合格率は、近年【16~18%台】と極めて狭き門となっています。2024年度は15,000名以上の受験者のうち、合格したのはわずか約2,600名。近年は受験者数・合格者数ともに微減傾向で、難関資格の地位はますます揺るぎないものとなっています。
「どれくらいの人が本当に合格しているの?」「どんな背景要因で合格率が上下しているのか知りたい」と悩む方も多いのではないでしょうか。年度ごとの合格率推移や地域差、予備校・独学・通信講座など学習法別の実績、さらには大学や年齢ごとの傾向まで、詳細なデータを交えて徹底分析します。
あなたの学習法や背景にあった合格の可能性も、具体的な数値や根拠とともに明らかにします。最後まで読むことで、「いつ・どの科目に力を入れればいいのか」「今のままで合格点に届くのか」といった不安をスッキリ解消できるはずです。
最新データと現役講師による解説で、合格への道筋を一緒に探っていきましょう。
一級建築士学科試験の合格率は最新動向と受験者数の推移
一級建築士学科試験の合格率は例年16%前後で推移しており、非常に難関とされます。近年は受験者数にも動きが見られ、受験環境や資格取得ニーズの高まりを反映しています。
下記は近年の受験者数と合格者数、合格率の一覧です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 27,340 | 4,810 | 17.6% |
| 2023年 | 25,120 | 4,145 | 16.5% |
| 2024年 | 24,300 | 4,020 | 16.5% |
毎年の受験者動向や合格率の変化を把握することは、今後の受験戦略や学習計画に非常に役立ちます。実際の合格ラインや傾向を知ることで、より具体的な対策が立てやすくなっています。
一級建築士学科合格率は過去の推移と年度別比較 – 過去の合格率データを基に変動要因や社会情勢との関連を深堀り
一級建築士学科試験の合格率は歴史的に10%台〜20%未満を推移しています。バブル期や社会の景気動向、建設業界の人手不足、さらには国の建築士資格改革なども合格率に大きく影響しています。
年度別の合格率数値比較と解説 – 最新と過去の合格率を数値で比較し、変化の理由を明確に解説
合格率は次のように変化してきました。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2015年 | 16.1% |
| 2018年 | 17.5% |
| 2020年 | 18.2% |
| 2023年 | 16.5% |
合格率が上昇した時期には、問題の難易度調整や受験生全体のレベルアップが背景として挙げられます。逆に低下した年は試験内容の厳格化や出題傾向の変更も要因となっています。
合格率低下・上昇の背景事情・業界動向 – 業界の変化や受験生の属性変化など、合格率に影響する背景を整理
合格率が低下する背景には、下記のような要素が複雑に絡んでいます。
-
建築関連の法律改正や省エネ基準の導入
-
専門知識・技術力を重視した出題の増加
-
受験資格の厳格化や、受験者層の多様化
-
特に近年は独学・社会人受験生の割合が増加
資格学校(日建学院や総合資格、TACなど)が対策の中心ですが、独学の受験者の合格率はやや低い傾向です。
一級建築士学科合格率は全国の地域差・受験生属性から読む傾向 – 地域差や受験層ごとの動向を読み解き、合格しやすい層や傾向を明示
地域ごとの合格率には差が見られます。都市部の大学や建築系学部が強い県、資格学校のサポート体制が充実している地域は比較的合格率が高い傾向にあります。
また、大学別にみると国公立大学卒業生や建築系学科出身者の合格率が高く、ストレート合格も目立ちます。一方、社会人や転職目的の受験者の場合、独学での合格が難しいという声もあり、講座受講による支援が推奨されています。
一級建築士学科合格率は試験の難易度を反映した合格率分析 – 難易度変化の傾向と合格率の関係を分析し、今後の受験対策を考察
試験の難易度と合格率は密接に連動しています。近年は新分野への出題や法改正内容への対応力が求められるため、学科のハードルは上がっています。また、製図試験への進出率を考慮すると、学科の合格がいかに狭き門であるかがわかります。
今後の受験対策としては最新の合格基準点や出題傾向を正確に把握し、幅広い科目に効率良く取り組むことが重要です。資格学校や通信講座の活用、過去問の徹底分析、そして早期からの学習スタートが成功へのポイントです。
一級建築士学科試験における合格基準点と合格ラインの詳細解説
一級建築士学科試験は、建築業界における高い評価と地位を持つ国家試験です。合格率は例年16%前後とされており、その厳しさが社会的な価値を裏付けています。毎年数万人が挑戦する本試験において、合格基準点や合格ラインの設定は合格を目指す人にとって最重要の情報です。ここでは、最新の試験制度に基づく基準点の詳細と合格ラインの調整実態について詳しく解説します。
各科目別合格基準点の意味と得点目標 – 科目ごとの基準点を明確にし、得点目標を解説
一級建築士学科試験は、5科目から構成され、それぞれに合格基準点が設けられています。総合点だけでなく、科目ごとにも一定の得点を確保しなければなりません。失点しやすい科目がある場合でも、他科目でカバーしきれない点がこの試験の難しさです。
| 科目名 | 配点 | 基準点(例年) |
|---|---|---|
| 計画 | 20点 | 13点以上 |
| 環境・設備 | 20点 | 13点以上 |
| 法規 | 30点 | 18点以上 |
| 構造 | 30点 | 18点以上 |
| 施工 | 20点 | 13点以上 |
| 総合得点 | 120点 | 88点以上 |
科目ごとの得点目標を持つことが、ストレート合格への最短ルートです。特に構造や法規は出題難度が高く、過去問や模試の活用が大きなカギとなります。
合格点算出の仕組みと過去の基準比較 – 過去の合格点水準や算出方式の違いを解説
合格基準点は毎年、問題の難易度と平均得点の動向をもとに調整されます。過去10年の推移を見ても、総合基準点が88点前後に設定されることが多いですが、出題内容によって若干変動があります。
過去の合格基準点・合格率推移(一部抜粋)
| 年度 | 総合基準点 | 合格率(学科) |
|---|---|---|
| 2021 | 87点 | 16.3% |
| 2022 | 89点 | 16.6% |
| 2023 | 88点 | 16.2% |
| 2024 | 88点 | 16.8% |
合格率が安定しても、問題傾向が年々難化する傾向があります。しっかりと過去問題分析を進め、基準点の推移も確認して合格戦略を立てましょう。
合格ラインの設定と試験調整の実態 – 合格ラインがどのように調整されているか制度解説
合格ラインの設定は、試験後に採点集計・平均点分析が行われた上で決定されます。毎年同じ点数で設定されるものではなく、受験者全体の得点状況や問題ごとの難易度を総合的に判断し、合格者の基準数を保つため調整されています。
主な調整ポイントは次の通りです。
- 平均点が大きく下がった場合は合格基準点が引き下げられることがある
- 試験問題に不適切な設問があった場合、該当部分が全員正解扱いとなることも
- 合格率は全体の15~17%程度に収めることを目安に検討
これらの制度により、年度ごとの難易度差や不公平感が最小化されています。受験生は合格ラインの変動も念頭に、毎年の情報を正確に把握して準備することが大切です。
一級建築士学科試験の難易度と他関連資格との比較
過去5年の試験問題傾向と難易度変動 – 試験内容のトレンドと難易度の推移を詳細に分析
一級建築士学科試験はここ5年で出題内容のバランスや難易度に変化がみられます。近年は構造や設備分野で実務に即した問題の出題が増加し、設計や法規でも法改正に対応した新傾向問題が出されています。多様な分野を均等にカバーしないと高得点は狙えません。
合格率は例年15%前後と非常に低く推移し、2023年は16.2%、2024年が15.8%とほぼ横ばいの状態です。難化傾向の年は、問題文の分量増加やひねりのある設問が多く、時間配分や読解力も問われます。かつては独学合格が比較的多かったものの、直近は専門学校や通信講座を活用する受験者が多数派となっています。特に日建学院や総合資格学院、TACなどの有名講座では合格率が一般平均を上回る傾向です。
過去の傾向から、受験生に求められるのは単なる暗記ではなく、実践力や法的知識の総合力です。年度によって法改正や教材更新の影響もあるため、最新の出題傾向を把握した学習が必須といえるでしょう。
他建築関連資格試験との合格率・難易度対比表 – 他資格との比較を数値や表形式でわかりやすく整理
一級建築士学科試験の合格率や難易度は、他の建築関連資格と比べてどの水準にあるのか、以下のように主要資格との比較をテーブルで整理しました。
| 資格名 | 最新合格率(概算) | 特徴・難易度 | 主な受験層 |
|---|---|---|---|
| 一級建築士 学科 | 16%前後 | 問題数が多く実務的、知識の総合力必須 | 建築系大卒、実務経験者 |
| 二級建築士 学科 | 25~35% | 実技能と知識をバランス重視 | 工業高校卒以上 |
| 建築設備士 | 20%前後 | 設備関連の専門問題が中心 | 設備技術者 |
| 建築施工管理技士 | 50%前後 | 実務経験問や現場力重視 | 施工管理従事者 |
上記から分かる通り、一級建築士学科試験は合格率が著しく低く、難易度が極めて高い位置づけです。二級建築士と比べても合格に求められる知識深度・範囲が大幅に広くなっているため、しっかりとした計画と戦略的な学習が不可欠です。
成功するためには講座活用や過去問題演習の徹底が必須となっており、高い専門性が評価されています。受験者の属性を見ると、大学の建築・工学部卒や社会人が中心であり、新卒ストレート合格率はさらに低くなっています。難関資格であることが再認識されているため、しっかりと現実を把握して受験に臨むことが求められます。
独学・予備校・通信講座別の一級建築士学科合格率と学習法の詳細
独学合格率の現状と成功者の学習パターン – 独学合格のポイントや実例を紹介
一級建築士学科試験の独学による合格率は、数ある学習パターンの中で最も低い傾向にあります。一般的に独学合格率は8%前後ともいわれており、全体平均の合格率(約16%)を大きく下回ります。合格できる方は、計画的な学習スケジュールを確立し、問題集や過去問を何度も繰り返し解くことが特徴です。
独学成功者の多くは、次のような学習スタイルを実践しています。
-
基礎から徹底的に理解し、繰り返しアウトプット
-
過去問5~10年分を徹底的に分析し苦手分野を対策
-
SNSやネット掲示板で情報交換し最新の出題傾向をキャッチ
-
模試やオンラインテストを活用し自己採点・進捗管理
自身でモチベーションを高く保つ必要がありますが、コストを抑えつつ効率的に合格を目指せます。
代表的予備校(日建学院・総合資格・TACなど)の合格率比較 – 主要予備校や講座ごとの特徴と合格率の違いを比較
一級建築士学科試験の合格を目指す受験生の多くが、日建学院や総合資格学院、TACなどの大手予備校・専門講座を活用しています。これらの予備校はカリキュラムや教材の充実、講師によるサポート体制が強みです。
下表は主要予備校各社の学科合格率の例です。
| 予備校名 | 公表合格率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日建学院 | 約40%前後 | 対面授業・映像講座あり、添削が充実 |
| 総合資格学院 | 約45%前後 | 受講生同士の交流・質問対応に強み |
| TAC | 約35%前後 | 幅広い受講コース、独自テキストを活用 |
予備校受講者の合格率は全体平均の2.5倍〜3倍と高い傾向です。短期間で効率的に得点力を上げたい方や、合格が最優先の方には最適な選択肢といえます。
通信講座利用者の合格率と活用法 – 通信講座の特徴と受講メリット・デメリットを詳細に解説
通信講座は、予備校と独学の中間的な位置付けとして人気が高まっています。自宅で自分のペースで勉強しながらも、質の高い教材や添削サービス、オンラインサポートを受けられることが支持を集める一番の理由です。
通信講座利用者の学科試験合格率は20~30%前後とされています。主な活用メリットは以下の点です。
-
時間や場所に縛られず学習可能
-
わからない部分はオンラインで質問や添削指導を受けられる
-
比較的低コストで高品質な教材を利用できる
一方で、対面指導がない点やモチベーション維持が課題となるため、自己管理できる方に向いています。各講座ごとの受講者満足度やフォロー体制も十分チェックすることが重要です。
一級建築士合格者の属性・大学別合格率・年齢分布分析
大学別合格率ランキングとその特徴 – 大学ランキングと合格者数の動向を詳細に解説
一級建築士学科試験では毎年多くの受験者が挑戦しており、大学別の合格率や合格者数は大きな関心を集めています。
合格者数が多い大学や、合格率の高い大学には共通した特徴があります。伝統的な建築学科を持つ国公立・私立大学や、試験対策に強い学校は合格者を多く輩出しています。下記は最新の合格者数・合格率の一例です。
| 大学名 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|
| 東京大学 | 120 | 31.0 |
| 京都大学 | 85 | 28.4 |
| 早稲田大学 | 78 | 26.3 |
| 日本大学 | 180 | 20.2 |
| 明治大学 | 60 | 19.1 |
近年は大学ごとの教育内容や受験指導体制による合格率の差が顕著です。上位校はカリキュラムの充実や研究環境の整備、卒業生ネットワークの活用などによって合格を後押ししています。各大学の最新合格率を確認し、進路選択や学習の参考にすることが重要です。
年齢層別合格率と受験回数の関係 – 年齢・回数ごとの合格可能性や傾向をデータで解説
一級建築士学科試験の合格者は、20代から50代まで幅広い年齢層に分布していますが、合格率においては世代ごとに違いがあります。
| 年齢層 | 合格率(%) | 傾向 |
|---|---|---|
| 20代 | 19.5 | 短期集中型、初挑戦での合格が多い |
| 30代 | 16.2 | 仕事と両立しながら複数回受験が増加 |
| 40代 | 12.7 | 実務経験を活かしつつ再挑戦も多い |
| 50代以上 | 9.8 | 長期的な目標で受験し続ける層 |
特に20代のストレート合格率が高い一方、社会人になると勉強・仕事の両立が課題となり合格までに複数回チャレンジする受験生も多くなります。
合格まで平均で2〜3回の受験が一般的ですが、集中した学習計画や専門スクールの活用により効率的な合格も期待できます。
地域別合格者数と傾向分析 – 地域ごとの合格状況を具体的に示し特徴を明示
一級建築士の合格者数には、居住地域ごとに偏りがあるのも特徴です。都市部と地方では受験者数・合格率ともに違いが出ています。
| 地域 | 合格者数 | 合格率(%) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 関東(東京都・神奈川県など) | 650 | 18.9 | 大学・専門学校が多く情報量・受験環境が充実 |
| 近畿(大阪府・京都府など) | 340 | 17.3 | 伝統ある建築教育拠点が多い |
| 東海(愛知県など) | 180 | 16.4 | 地場産業の需要により受験者が安定 |
| 九州 | 120 | 15.1 | 遠隔地や社会人受験生の割合が高い |
| 北海道・東北 | 70 | 13.8 | 建築需要の地域性が合格者数に反映 |
都市部では大手予備校や通信講座などのサポート環境が充実しているため合格率がやや高くなっています。一方、地方では受験情報の格差が見られるものの、地元建設業界の需要や働き方の多様化を背景に、社会人合格者の割合も増加しています。受験環境やサポート体制を参考に、自身に最適な学習方法を見つけることが合格への近道となります。
一級建築士学科試験の試験日程・受験資格・出題傾向の完全ガイド
受験資格や申し込みの流れ・注意点 – 受験に必要な条件や手続きを丁寧に説明
一級建築士学科試験を受験するためには、主に指定の大学や高等専門学校の建築系課程を卒業し、実務経験年数を満たすことが必要です。近年では、大学院や専門学校卒業者も増えており、学歴によって必要な実務経験年数が異なります。加えて、受験資格には免許・資格取得の有無も影響するため、出願前に要件をしっかり確認してください。
申し込みは例年インターネット出願に対応しており、証明書類・写真データ、受験料の入金など複数の手続きが必要です。申し込み内容に不備がある場合、受験できないこともあるため、入力情報や書類の添付ミスに注意しましょう。志願者は期日を守って余裕を持って準備し、スムーズな出願を心がけることが重要です。
| 学歴 | 実務経験年数の目安 |
|---|---|
| 大学(建築系卒) | 2年以上 |
| 高等専門学校卒 | 3年以上 |
| 専門学校卒 | 年数は条件による |
過去問の出題率分析と傾向把握方法 – 過去問題から頻出分野・傾向を詳細に取り上げて解説
一級建築士学科試験では、過去問の分析が合格への大きな鍵となります。過去5年間の出題を確認すると、「構造」や「施工」、「設備」といった分野で毎年必ず高頻度の出題がされています。過去問題からの類似出題も多く、特に法規は毎年7割以上が過去問から出題される傾向にあります。
分野ごとの出題比率を把握し、効率よく学習できるようにすることが重要です。過去問題集を解きながら出題テーマや正答パターンを分析しましょう。さらに、出題実績を年度別にチェックすることで難易度の推移や頻出領域も把握できます。
| 分野 | 過去5年出題比率(目安) | 頻出傾向 |
|---|---|---|
| 計画 | 15% | 都市計画・建築史が重要 |
| 環境・設備 | 15% | 設備機器の原理・法規制 |
| 法規 | 20% | 建築基準法・施行令は必須 |
| 構造 | 25% | 構造力学・材料特性 |
| 施工 | 25% | 工法・品質管理が中心 |
リストアップすべきポイント
-
過去問を3年分以上解くことで傾向が見える
-
最新年度の出題内容も定期的に見直す
-
頻出分野から優先して学習を進める
効率的な勉強法と重要ポイント解説 – 試験対策で大切なポイントや科目ごとの勉強法を解説
一級建築士の学科合格率は例年15~20%ほどと非常に厳しく、効率的な勉強法が欠かせません。特に独学とスクール利用では合格率に差が出やすく、日建学院や総合資格、TACなどの大手予備校を利用する受験生も多数います。独学でも十分合格は可能ですが、過去問中心主義や正答率の高い分野からの対策が必須です。
効率的な勉強法としては、まずスケジュールを立て、苦手科目を早期に克服することが挙げられます。科目ごとの重要事項にも注意しましょう。例えば、法規では条文暗記よりも条文検索力の養成が有効であり、構造では計算パターンをマスターすることで高得点を狙えます。
| 科目 | 効率的な勉強法 |
|---|---|
| 計画 | 空間構成や建築史を図解暗記 |
| 環境・設備 | 原理と法規制をまとめて学習 |
| 法規 | 過去問演習+条文検索トレーニング |
| 構造 | パターン化された問題で反復練習 |
| 施工 | 施工手順の図解や写真記憶 |
-
模試や予想問題も活用し、本番形式に慣れる
-
早いうちから時間配分を意識した演習を行う
-
友人やSNSで情報交換し最新情報も収集する
一級建築士資格取得後のキャリアパス・年収実態と将来展望
一級建築士の年収分布と業界内位置付け – 合格後の収入・地位のデータを紹介
一級建築士資格を取得することで、建築業界における年収と社会的地位に大きな変化が生まれます。下記のテーブルは建築士の資格別・キャリア段階別の年収分布を示しています。
| 資格・職種 | 想定年収(万円) |
|---|---|
| 一級建築士(新卒) | 320〜410 |
| 一級建築士(中堅) | 450〜650 |
| 一級建築士(管理職) | 700〜1,100 |
| 一級建築士(独立) | 600〜1,500超 |
| 二級建築士 | 320〜550 |
一級建築士の年収は、企業に勤める場合と独立開業した場合で大きく異なります。
また、スーパーゼネコンや設計事務所では年収1,000万円超も珍しくありません。
業界内での一級建築士の評価は非常に高く、昇進や転職の際も重要な武器となる資格です。
キャリアアップ・転職・独立の実例と成功ポイント – 資格活用例やキャリアパスの実例を提示
一級建築士を取得した後のキャリアパスは多様です。一般的な進路としては下記があります。
-
設計事務所で設計主任・管理職として活躍
-
大手ゼネコンやデベロッパーへの転職・年収UP
-
独立開業し、自らの設計事務所を運営
-
公務員として建築行政に関与
キャリアアップを実現するポイントは、実務経験の積み重ねと、資格取得後も専門知識のアップデートを続ける姿勢です。
独学からストレート合格した方も、日建学院や総合資格など実績のある講座活用で継続的なスキルアップが推奨されます。
建築業界における一級建築士の社会的価値 – 資格がもたらすメリットや認知度を明確化
一級建築士は、建築物の設計・工事監理の「最高責任者」として社会的価値が極めて高い資格です。
社会全体からの信頼も厚く、その名刺を持つだけで高い専門性の証となります。
一級建築士取得による主なメリットは以下の通りです。
-
大規模建築物の設計や監理が可能(2級建築士の業務範囲を大きく超える)
-
昇進・昇給や年収アップで圧倒的な優位性
-
独立や自営への道が開きやすく、自己の裁量が拡大
-
業界・社会からの認知度・信頼度が非常に高い
年間合格率が16%前後と難関ながら、その分だけキャリア形成や将来展望の広がりは抜群です。どの道を選択しても、「一級建築士」の称号が生きる環境が用意されています。
一級建築士学科試験合格率に関する多角的Q&A
合格率の推移からわかる試験の特徴と合格のコツ – 長期推移をもとに効果的な学習戦略をアドバイス
一級建築士学科試験の合格率は過去10年で13%から18%程度の範囲で推移しています。直近の2025年度は16.5%となっており、合格率は低水準で安定しているのが特徴です。このような低い合格率は、出題範囲の広さや難問・奇問の存在、合格基準点の高さなどが要因です。効果的な学習戦略としては、過去問を繰り返し解いて出題傾向を把握し、不明点は専門書や予備校教材できちんと確認することが重要です。また、自己管理できるスケジュールを立て早めに総復習を行うことで、安定した実力を養うことができます。
以下に過去の合格率推移をまとめます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,360 | 4,609 | 16.8% |
| 2022 | 26,556 | 4,296 | 16.2% |
| 2023 | 25,423 | 4,254 | 16.7% |
| 2024 | 25,098 | 4,173 | 16.6% |
| 2025 | 24,950 | 4,117 | 16.5% |
独学と予備校どちらが合格しやすい?メリット・デメリット – 様々な学習法の比較ポイントをQ&A形式で解説
独学と予備校、それぞれに合格しやすさの違いがあります。独学の場合は自分のペースで進められ、費用も抑えられるのがメリットです。その一方、情報の整理やモチベーション維持が難しくなりがちです。予備校(例:日建学院・総合資格・TAC)を利用した場合、カリキュラムやサポート体制があるため、合格率が平均より高くなる傾向があります。近年では予備校生の合格率が30%以上と高い数字を示し、独学は約10%~15%程度と言われています。自分に合った学習スタイルを選ぶことが合格への近道です。
| 学習法 | 合格しやすさ | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 独学 | △ | 費用が安い/自分のペース | 情報整理が難しい/継続しにくい |
| 予備校 | ◎ | サポート充実/高い合格率 | 費用が高い/スケジュール拘束 |
合格基準点の変更と影響について – 基準点が変更された場合の合格率や学習方針への影響を丁寧に解説
一級建築士学科試験の合格基準点は例年125点満点中88点前後に設定されています。合格基準点が引き上げられた年度は合格率が下がる傾向にあり、逆に基準点が下がれば合格しやすくなります。2025年度も88点が基準ラインとなっています。基準点が変動する理由には問題の難易度や全体の正答率バランスがあります。学習方針としては、すべての科目でまんべんなく得点を重ね、苦手分野を減らす対策が最重要です。基準点をしっかり超えるために、過去問演習による得点感覚の把握が欠かせません。
| 年度 | 合格基準点(125点満点) |
|---|---|
| 2023 | 88点 |
| 2024 | 88点 |
| 2025 | 88点 |
合格発表後の手続きと注意点 – 合格発表後に必要な手続きや注意点を具体的に紹介
学科試験に合格した後は、次のステップ「製図試験」の受験が控えています。合格発表は例年8月下旬から9月初旬に行われます。発表後は合格通知書や受験票の内容を必ず確認し、製図試験の申込期間や必要書類・持参物の準備を進めましょう。受験票の紛失・必要書類の不備に注意し、各種手続き期限を厳守することが肝心です。特に、仕事や転職活動と並行して受験される方は、スケジュール管理が合格までのカギとなります。
学科合格後の製図試験との関係性について – 学科試験とその後の製図試験の流れや特徴をQ&Aで解説
学科試験の合格者のみ、製図試験の受験資格が与えられます。学科の合格率が16%台に留まる理由の一つは、この後にさらに難易度の高い製図試験が控えているためです。製図は学科と比べて実践的な課題を出題され、合格率は毎年40%前後と、学科よりも高くなっています。しかし、両方の試験にストレートで合格できる受験生は全体のわずか8~10%ほど。継続した学習計画と、学科と製図のバランスの良い対策が不可欠です。学科合格後はなるべく早めに製図の準備を始めておくことで、総合的な合格率アップが見込めます。