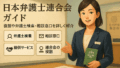大手企業の決算書は、実は【年間およそ4万社】が公認会計士によって厳格に監査されています。なぜ、ここまで多くの会社が会計士の目を必要とするのでしょうか?
「本当に専門性が高い仕事なの?」「資格を取っても将来性はある?」といった疑問を抱えていませんか。公認会計士の年収は【平均800万円台】といわれ、20代・30代でも管理職に抜擢される機会があります。しかし一方で、働き方やワークライフバランス、資格取得までの負担や合格率【10%前後】といった現実的な壁も。
会計・監査・コンサルティングと多岐にわたる専門性、変わり続ける業務内容、増加する女性会計士や新しいキャリアパス。
このページでは、「公認会計士の仕事とは何か」を基礎から具体的な数字や最新動向まで、わかりやすく徹底解説します。ここを最後まで読めば、あなたが抱えていた「本当に向いているのか」「どんな将来像なのか」といった不安や迷いもクリアになります。
公認会計士とはどんな仕事か?基礎から専門性まで幅広く解説
公認会計士の資格概要と役割
公認会計士は、経済社会における財務情報の健全性を守る専門職です。主な仕事は企業や法人の財務諸表を客観的に監査し、正確さや信頼性を保証することにあります。これにより投資家や取引先が安心して経済活動を行える環境を実現します。特に上場企業の監査業務は公認会計士の独占業務であり、その社会的責任は非常に大きいです。
さらに、会計や税務のプロフェッショナルとして、企業の経営戦略や財務内容のアドバイスも行います。独立性と高い専門性が求められる仕事であり、法律や国際基準に即した判断力も必要です。財務の専門家として多方面で活躍しています。
会計士・公認会計士・税理士の違い
会計士、税理士、公認会計士には明確な違いがあります。公認会計士は会計監査を法的に行える唯一の資格です。一方、税理士は税務申告や税務相談を専門とし、企業や個人の税金に関する手続きや指導を担います。
下記のテーブルで主な違いを整理します。
| 資格名 | 主な業務内容 | 必要な資格・登録 |
|---|---|---|
| 公認会計士 | 財務諸表監査、会計指導 | 公認会計士試験合格、登録 |
| 税理士 | 税務申告、税務相談 | 税理士試験合格または登録 |
| 会計士(一般) | 会計記帳、決算代行 | 簿記等の資格が中心 |
このように業務範囲や必要な専門知識が異なり、どちらが難しいかは目的や業務内容で変わります。公認会計士が税理士登録することで、業務の幅が大きく広がります。
税理士登録の意味と業務範囲拡大の具体例
公認会計士が税理士登録を行うと、税務業務が可能となり、クライアントの税務申告や節税アドバイスまで担当できます。経営者からは、会計や監査だけでなく、直接の節税対策や税務相談も求められるため、税理士登録によって付加価値が大きくなります。
具体的には、税務調査の立ち会い、会社設立時のアドバイス、複雑な相続税案件まで対応可能です。公認会計士だけでは対応できない税務分野をカバーし、多様なニーズに応じた専門的な支援が可能となります。
公認会計士の社会的な必要性と使命感
公認会計士は企業や団体の財務透明性を守る「経済社会の守護者」とされています。不祥事や会計不正が発覚した際には、社会全体の信頼を回復する役割も担います。会計や税務の専門知識を活かして、企業経営の健全化や資本市場の発展に寄与していくことが強く期待されています。
社会的使命感が大きい分、業務の責任も重く、厳しさを感じる一面もあります。しかし、経済の土台を支える仕事としてやりがいや成長実感を得やすい職業です。ユーザー視点の誠実なサービスが必要不可欠であり、多くの公認会計士が誇りを持って日々業務にあたっています。
公認会計士の主要な仕事内容を深掘り解説
公認会計士は社会の経済活動の信頼性を担保する専門家です。主な仕事は監査業務、税務業務、コンサルティング業務、そして組織内会計士としての活躍です。多様なフィールドで、企業や個人、社会に貢献する職業であり、専門知識と高い倫理観が求められます。近年はAIやDXの波も業界に押し寄せていますが、それでも公認会計士は「数字の正確さ」「透明性」を守る立場として評価されています。以下で各業務ごとに詳細に解説します。
監査業務の実際と戦略的役割
公認会計士の象徴的な業務が監査業務です。監査では企業の財務諸表を厳しく精査し、その内容が適切かつ公正に作成されているかをチェックします。特に上場企業などは年次監査が法令で義務付けられており、監査報告書の発行責任を負います。
主なポイントは以下の通りです。
-
企業が報告する数値の信頼性・透明性を証明
-
経営者と独立した立場でチェックを行う
-
社会的に重要な会計不正防止の抑止力となる
-
間違いや粉飾の発見だけでなく、内部統制の助言も行う
この独占業務によって、投資家や取引先、社会全体からの信頼を集めています。
税務業務の概要と税理士登録の活用
公認会計士は税理士登録を経て税務業務も担当できます。税務業務では企業や個人の税務申告書の作成、税務相談、節税アドバイス、国税局への書類提出代理などを行います。
ポイントを絞ると下記の通りです。
-
税理士登録後、税理士業務が可能
-
法人税・所得税・消費税など多様な税務対応
-
税金面での戦略的サポートや節税対策の立案
-
経営アドバイザーとして企業に並走
会計業務で培った知識を活かし、数字のプロとしてクライアントの資産を守ります。
コンサルティング業務の多様性
コンサルティング業務は、公認会計士の専門知識を活用した経営支援に該当します。監査や税務とは異なり、より広範囲で現場の課題解決に取り組みます。
下表は主なコンサルティング業務の領域です。
| コンサルティング領域 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 経営戦略・財務アドバイス | 資金調達・M&A・事業再生・財務分析 |
| 内部統制・業務改善 | 業務プロセス最適化・社内ルール構築・リスクマネジメント |
| 事業承継・相続 | 企業の事業承継・資産承継・相続対策 |
| IT・システム支援 | 会計システムの導入・仕事のデジタル化支援 |
各分野ごとに高い専門性とコミュニケーション能力が求められます。クライアントの目標達成を現実的かつ持続可能な形でサポートできるのが強みです。
組織内会計士の役割
公認会計士のキャリアは監査法人や税理士法人だけでなく、企業内会計士としても広がっています。組織内では経理部門や財務管理部、経営企画部などで様々な業務を担当します。
役割例をリストアップします。
-
連結決算や開示資料の作成とチェック
-
予算編成・財務分析・資金調達サポート
-
経営層に向けた経営判断材料の提供
-
内部統制やガバナンス強化の旗振り役
多様なビジネスシーンで専門性を活かし、「会社の未来を数字で支える」存在となっています。働き方の柔軟性もあり、ライフスタイルに合わせてキャリアを築ける点も評価されています。
典型的な公認会計士の一日の仕事の流れ
朝からの業務スケジュール例
公認会計士の朝は、監査法人や勤務先の会社によって多少異なりますが、多くの場合は出社後すぐにチームミーティングで一日の作業内容や進捗状況の共有から始まります。クライアント企業の財務諸表や会計帳簿のチェック、残高確認などのルーティン業務を行い、その日の訪問先やプロジェクトごとにやるべき業務を明確にします。
特に監査期間中は、企業訪問や資料収集が多く、担当企業の担当者と打ち合わせしながら監査手続きを進めます。
| 時間 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 9:00 | チームミーティング、当日のスケジュールや監査計画の確認 |
| 10:00 | クライアント先へのメール確認、会計資料の精査 |
| 11:00 | 必要に応じて企業訪問、現場ヒアリング |
午前中は集中力が必要な作業が中心で、財務書類の確認や監査証拠の収集など専門性の高い業務が進みます。
午後から夕方までの業務内容
昼食後は、午前中に収集した監査証拠や資料を基に分析業務を行います。担当チームごとに進捗報告を行い、必要であれば上司やクライアントと打ち合わせを重ねます。
午後は訪問先での会議や不明点の確認、監査調書の作成が主な業務です。資産評価や内部統制の確認、監査報告書の作成に向けた最終チェックも行います。
業務の流れ
- 監査調書の作成
- 担当案件の進捗管理
- クライアントや上司と最終チェック、質疑応答
会計士の仕事は1日の中でも幅広く、会計の知識やビジネス全般に関する理解力が求められます。
繁忙期・閑散期の業務負荷とワークライフバランス
公認会計士の仕事は時期によって大きく業務量が変動します。決算期や税務申告期になると監査や申告業務が集中し、繁忙期には連日遅くまで働くことも少なくありません。一方、閑散期は業務が落ち着き、休暇をとったり自己研鑽や資格勉強の時間に充てられる場合も多いです。
| 時期 | 業務量 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 繁忙期 | 非常に多い | 決算監査、税務申告、長時間労働 |
| 閑散期 | やや少ない~平均 | 社内研修、内部監査、自己研鑽 |
ワークライフバランスに対する職場の取り組みも進んでおり、各法人によっては労働時間の適正化や有給取得促進に力を入れています。
多様な勤務スタイルとリモートワークの導入状況
近年では働き方改革の影響もあり、監査法人や企業によってはリモートワークやフレックスタイム制度が導入されています。会計士の業務はオンラインで資料確認やミーティングが可能なものも多く、場所を選ばず働くことが容易になりました。家庭やプライベートの時間を重視する方にも適した環境も増えています。
主な勤務スタイルの例:
-
フルタイム勤務(監査法人や企業内会計士が中心)
-
時短勤務や育児・介護との両立が可能なケース
-
リモートワーク中心のチームやプロジェクトベースの働き方
このように、公認会計士は多様なキャリアや働き方を選択できる専門職です。今後もライフスタイルに合わせた選択肢が拡大すると期待されています。
公認会計士の年収事情とキャリア別収入モデル
公認会計士の年収相場と影響要因
公認会計士の年収は、キャリアステージや勤務先、役職などによって大きく変動します。新卒やジュニアスタッフの場合、年収は約400万円〜600万円が一般的です。シニアスタッフやマネージャークラスになると、年収が800万円から1,200万円以上になるケースも増えます。また、ビッグ4と呼ばれる大手監査法人では待遇が比較的高い傾向があります。
年収に影響を与える主な要因は以下の通りです。
-
法人規模(中小監査法人か大手か)
-
勤務地(東京の方が地方より高い傾向)
-
役職・経験年数
-
急激な繁忙期や業界景気
近年は働き方改革も進み、ワークライフバランスに配慮した制度を導入する企業も増加しています。
| ポジション | 年収目安 |
|---|---|
| 新卒・未経験 | 400万〜600万円 |
| シニア | 700万〜1,200万円 |
| マネージャー | 1,200万〜1,500万円 |
| パートナー | 2,000万円以上 |
女性公認会計士の年収と働き方
女性公認会計士も着実に増えており、年収やキャリア選択肢において男女格差は徐々に縮まっています。仕事内容自体は男性と同じですが、ライフイベントや育児と両立しやすい企業も多く、リモートワークや時短勤務も積極的に導入されています。
代表的な女性の働き方は以下の通りです。
-
監査法人での監査業務
-
企業内会計士として経理や内部監査
-
税理士資格を活かした税務やコンサルタント
年収の目安も男性と同水準であり、家庭と両立している方も多いです。また、専門性の高さから再就職や転職時にも有利な点が評価されています。
高収入・経営幹部になるケース
公認会計士が高年収を実現するには、監査法人でパートナーになる以外にも多様なルートがあります。特に以下のケースで高収入が期待できます。
-
監査法人のパートナーポジション(2,000万円以上)
-
一流企業のCFOや経営幹部としての転職
-
独立開業して税務・会計事務所を経営
年収1億円を超える事例もまれに見られますが、これは経営層や極めて成功した独立開業の例です。近年はAIやシステム化が進む中でも、専門的な判断力や経営戦略のアドバイザーとして市場価値を高める公認会計士が増えています。役職や業界を問わず、専門性とネットワークの広さがキャリアアップには不可欠です。
公認会計士になるための具体的ステップと試験の実態
公認会計士試験とはどんなものか
公認会計士になるには、まず国家試験である公認会計士試験に合格する必要があります。この試験は「短答式」と「論文式」という二段階で構成されており、どちらも高い専門性と論理的思考力が問われます。短答式は主に会計学・監査論・企業法などの基礎知識、論文式は実務に即した記述力や応用力を確認する内容です。いずれも幅広い知識が必要となり、会計や経済、法務に関する徹底的な学習が求められます。
この資格は年齢や学歴に関係なく挑戦できる点が特長で、社会人や学生からも人気があります。また、「監査」「税務」「コンサルティング」など幅広い将来のキャリアに直結するため、多くの人が目指しています。
難易度や合格率の現実的な数字
公認会計士試験の難易度は非常に高いことで知られています。各年度ごとに合格率は異なりますが、目安として短答式試験の合格率は10~15%台、論文式試験は30%前後となっています。全体を通しての最終合格率は、およそ10%前後が一般的です。
この厳しい数字からも分かる通り、合格には長期間にわたる計画的な学習が不可欠です。複数年にわたり受験する人が多く、一度で合格を目指す場合は徹底した準備が求められています。こうした背景もあり「公認会計士 やめとけ」や「無理ゲー」といった再検索ワードも見られる一方、合格者は大きなキャリアアップや年収アップを果たす人が多いのも特徴です。
効果的な勉強法と費用相場
効率的な勉強法としては、独学または専門学校・通信講座の活用があります。
独学の場合、参考書や問題集が情報源となりますが、膨大な試験範囲と最新の試験傾向への対応が難しい点に注意が必要です。
一方、専門学校や予備校に通う場合は体系的なカリキュラムを通じて学習でき、効率的かつ高い合格率が期待できます。
公認会計士試験対策にかかる費用相場は以下の通りです。
| 学習方法 | 費用目安 |
|---|---|
| 独学 | 3万円~10万円程度 |
| 通信教育 | 10万円~40万円程度 |
| 専門学校・予備校 | 40万円~70万円程度 |
学習期間は通常2~3年が目安とされ、毎日の継続的な学習が重要です。仕事と両立しながら勉強する受験生も多く、スケジュール管理とモチベーション維持も合格のポイントです。
学歴不要か?高校・大学・中学生からの挑戦
公認会計士試験には、年齢や学歴の制限はありません。そのため、高校生や大学生はもちろん、中学生でも必要な知識とやる気があれば挑戦できます。実際、近年では最年少合格者が10代で登場するなど、幅広い年代が目指せる国家資格となっています。
また、大学に通いながら試験勉強を進める人も増えており、自分のペースで学習を開始できます。ポイントは、早いうちから会計や簿記の基礎を身につけることです。社会人からキャリアチェンジを目指すケースも珍しくありません。自分に合った学習方法やスケジュールで計画的に取り組むことが合格への近道です。
公認会計士の多様なキャリアパスと活躍の場
監査法人や税理士法人などの主たる就職先
公認会計士の代表的な就職先は、監査法人や税理士法人です。監査法人では企業の財務諸表が正しく作成されているかを監査し、社会や投資家の信頼を守ります。上場企業の法定監査や内部統制の評価、M&A監査など多様な業務を通じてキャリアを積めます。税理士法人では、法人税や所得税の申告、税務相談、相続対策など税金に関する幅広いサービス提供が可能です。税理士資格を併せ持つことでダブルライセンスの強みが発揮され、年収アップやキャリアの幅拡大にもつながります。
| 就職先 | 主な業務 | 特徴 |
|---|---|---|
| 監査法人 | 監査業務、財務諸表レビュー | 組織的で案件数が多く、成長機会が多い |
| 税理士法人 | 税務申告、税務コンサルティング | 顧客企業の税務プランニングや相続対策が可能 |
一般企業や官公庁での会計士の活躍
近年は一般企業や官公庁へのキャリアも広がっています。企業の経理部門や経営企画部での会計管理、財務戦略の立案、決算対応など重要な役割を担います。とくに上場企業では国際会計基準への対応やグローバルな資金調達など専門知識が活かされます。官公庁では会計監査や税務の法令整備、財務管理の支援を行う場面があり、社会的意義の高い仕事が求められます。近年は経営層やCFOとしての進出も目立ち、幅広い分野での活躍が期待されています。
-
一般企業:経理、財務、IR(投資家対応)、管理会計、経営企画
-
官公庁:会計検査院、国税庁、地方自治体の財務部門
独立開業とダブルライセンス活用
公認会計士は独立開業も選択できます。会計事務所や税理士事務所を設立し、企業や個人の経営・税務コンサルティング、事業承継サポートなど多岐にわたるサービスを提供できます。税理士や社会保険労務士、中小企業診断士などの資格と組み合わせたダブルライセンスで、業務範囲を広げる事例も増えています。独立後は柔軟な働き方や高収入を目指せる一方、営業力や専門分野の強みが必要です。女性会計士の独立も増加傾向にあり、出産や子育てにあわせた柔軟なキャリア形成も可能です。
-
独立開業の主な業務例
- 決算書・申告書作成
- 経営相談・事業計画策定
- 相続・資産税対策
- 企業再生・M&Aアドバイザー
業界動向と将来的なキャリアの見通し
公認会計士業界ではAIやデジタル技術の進展が進み、自動化による効率化とともに、人間にしかできない高度な判断力が一層求められています。監査や税務の基本業務は今後も一定の需要がありつつ、企業再生や経営コンサルティングなど新しい活躍分野が拡大しています。将来的にはグローバルライセンスとしての需要や、英語・ITスキルを活かした専門特化の道も注目されています。一方で、「公認会計士 仕事なくなる」「将来性 ない」といった不安も聞かれますが、社会の信頼が必要な以上、監査や専門アドバイザーの役割は今後も継続する見通しです。変化に対応したスキルアップが、キャリアの選択肢を広げる鍵となります。
| 未来の注目ポイント | 概要 |
|---|---|
| AI・技術進化への対応 | 自動化・IT化で業務効率アップ、多様な専門分野への対応力が必須 |
| 国際会計・英語力の必要性 | グローバル企業対応、英語・国際基準対応で市場拡大 |
| コンサルや戦略分野への職域拡大 | 経営支援、再生支援、内部統制強化などで新しい活躍の余地 |
公認会計士のリアルなメリットと課題
公認会計士としてのやりがい・達成感
公認会計士のやりがいは、厳格な監査を通じて企業や経済社会の信頼を支える点にあります。多くの責任を伴う分、企業の財務情報の信頼性を保証することで、資本市場の健全な発展に直接関わることができます。また、財務や税務、コンサルティングなど多岐にわたる業務があり、自身の専門性を高めながら幅広いキャリアパスが選択できる点も大きな魅力です。
公認会計士として働くメリットをわかりやすく比較すると、以下のようになります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 専門性と社会的信頼 | 高度な資格と社会的信用を獲得できる |
| 幅広い活躍フィールド | 監査法人・一般企業・独立開業・コンサル業務など多彩 |
| 安定した収入と将来性 | 高い年収水準、将来的な独立や転職にも有利 |
| やりがいと社会貢献 | 経済全体の健全性維持に貢献し、企業支援にも携われる |
仕事の厳しさと課題
公認会計士の仕事は、繁忙期や決算期の多忙さ、膨大な会計基準や税法への理解が求められる点で厳しさを伴います。特に、大手企業の監査を担当する場合には膨大な量の書類確認や内部統制評価が発生し、責任の重さやプレッシャーも大きいです。
よく挙げられる課題をリストで整理します。
-
強いプレッシャーや責任感
-
長時間労働・繁忙期の業務量
-
法改正や会計基準の頻繁なアップデートへの対応
-
クライアント対応スキルや柔軟なコミュニケーション力も必須
これらの課題を乗り越えるには、確かな知識と継続的な自己成長意欲が求められます。
実際に辞めた人の声や理由
公認会計士を実際に離れた人の声としては、以下の理由が多く挙げられます。
-
仕事とプライベートの両立が難しい
繁忙期には休日出勤や残業が増えるため、家庭やプライベートとの両立が難しくなりやすいです。 -
業務の単調さやミスへの不安
毎年の決算期ごとの業務が繰り返しになるため、やりがいを感じづらくなる場合や、ミスを許されない環境への精神的プレッシャーから転職を考える方もいます。 -
キャリアの壁や将来への不安
AIやIT技術の進展による仕事の将来性への不安や、管理職への昇進が難しいとの悩みもよく見られます。
続けるための工夫と心構え
長く公認会計士として活躍するためには、自ら意識して働き方やキャリア設計を見直すことが重要です。
-
定期的な休息・趣味の時間を確保する
-
チームで協力できるコミュニケーションスキルの習得
-
最新の会計知識・ITスキルのアップデート
-
中長期的なキャリアプランを描く
公認会計士として求められる適性は、論理的思考力や責任感、学び続ける意欲です。社会の変化にも柔軟に対応しながら、専門性と人間力を両立できる人が長く働き続けられます。
公認会計士の将来性とテクノロジー・AIの影響
AI・自動化技術の現状と公認会計士への影響
近年、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの自動化技術が会計業界でも急速に導入されています。これにより、従来公認会計士が手作業で行っていた仕訳入力や経理処理などの単純作業は、AIによる自動化が進んでいます。特に大量のデータを扱う監査現場では、AIが異常検知や不正リスクを迅速に分析できるため、作業の効率化と精度向上につながっています。
下記の表は、AI導入状況と会計業務への影響をまとめたものです。
| 項目 | AI実装状況 | 公認会計士への影響 |
|---|---|---|
| 仕訳入力 | 高 | 作業時間の短縮 |
| 会計データ分析 | 高 | リスク分析の精度向上 |
| 財務諸表チェック | 中 | ミスの削減・品質向上 |
| コンサルティング | 低 | 専門性・判断力が引き続き必須 |
このような変化により、単純作業の負担は減る一方、本質的な専門知識や判断力を問われる業務に注力することが求められています。
職務が変わるだけ?消える業務と残る業務
AIや自動化技術の普及により、公認会計士の業務は変化しつつあります。消える業務と、今後も求められる業務は次の通りです。
消える業務
-
定型的な仕訳や伝票入力
-
金額チェック・帳簿突合等の単純作業
-
ルーティン化された帳票の確認作業
残る業務
-
財務諸表監査などの法的責任を伴う業務
-
高度な判断や専門知識を要するコンサルティング
-
内部統制評価、リスクマネジメント
-
顧客ごとのカスタマイズされた税務支援
AIによって一部の業務は効率化されても、監査法人における監査やコンサルティングの分野では、今後も公認会計士の役割は不可欠です。また、法規制や企業独自の事情に対応する柔軟性やコミュニケーション能力もより重視される傾向にあります。
これからの公認会計士に求められる能力・スキル
これからの公認会計士に必要とされるのは、単なる会計知識だけではありません。テクノロジーの進化を活かし、高度なスキルと多様な能力を身につけることが重要です。
- データ分析力
AIやITシステムを活用したビッグデータ解析力は今後不可欠です。異常値の把握やリスク分析を論理的に行う力が求められます。
- ITリテラシー
監査ツールやクラウド会計など、新しい技術に柔軟に対応するスキルが必要です。
- 高度なコミュニケーション力
企業の経営層や現場担当者との折衝や、適切なアドバイスを行う能力がより重視されます。
- 倫理観と判断力
増えるAI活用の中で、最終的な判断や責任を持つのは公認会計士自身です。社会的信頼を守るため、強い倫理観が不可欠です。
これらの力を磨き続けることで、AI時代でも価値のある専門職として活躍し続けることができます。
公認会計士に関する具体的疑問をわかりやすく解説
子どもや初心者にも分かる公認会計士の仕事解説
公認会計士は、主に企業の財務書類が正しく作成されているかを第三者の立場からチェックし、信頼できる証明を行う専門家です。仕事は大きく分けて監査、税務、コンサルティングの三つがあります。
- 監査業務:企業の売上や利益などの数字が正しいかを調べます。
- 税務業務:税金に関する相談や、確定申告の手伝いを行います。
- コンサルティング:経営の改善やアドバイスをします。
このような仕事を通じて、企業や社会の信頼性と透明性に貢献しています。
公認会計士になるために必要な学力や学歴
公認会計士になるには難易度の高い国家試験に合格する必要があります。大学や学部に制限はなく、高校卒業後や社会人からでも挑戦可能です。学歴よりも、幅広い会計知識や法律の理解、論理的思考力が重視されます。受験には簿記や財務会計の基礎知識が必須で、独学や予備校利用など学習方法は人それぞれです。
| 受験資格 | 年齢・学歴の制限なし |
|---|---|
| 必要知識 | 簿記、会計、法律、経営など |
| 合格率 | 平均で10~15%程度 |
しっかりと準備し努力すれば、出身校や文系理系に関わらず十分に合格が目指せます。
女性公認会計士の実態と働きやすさ
公認会計士は女性にも人気が高まり、働きやすい職種です。監査法人や企業の管理部門、会計事務所などさまざまな就職先があり、時短勤務やテレワークができる環境もあります。妊娠や出産後の復職もしやすく、ワークライフバランスも取りやすいのが特徴です。女性管理職やパートナーとして活躍する事例も増えています。ライフイベントに柔軟に対応でき、やりがいと安定性の両立がしやすい職業です。
資格取得後に後悔しないための注意点
公認会計士資格は非常に価値がありますが、実務は責任が重く、繁忙期は長時間労働になることもあります。「仕事がきつい」「食えない」「将来性がない」といった声も一部にありますが、企業数や業界の変化により状況は大きく異なります。AIやシステム化の進展で業務内容が変わる場面もあり、継続的な学習と情報収集が重要です。
-
給与・待遇は経験や職場で大きく異なる
-
キャリアの多様化を常に意識する
-
新しい分野にチャレンジする姿勢が大切
自分に合った働き方やキャリアパスを明確に描き、常に経済や会計の最新動向に関心を持つことが後悔しないポイントとなります。