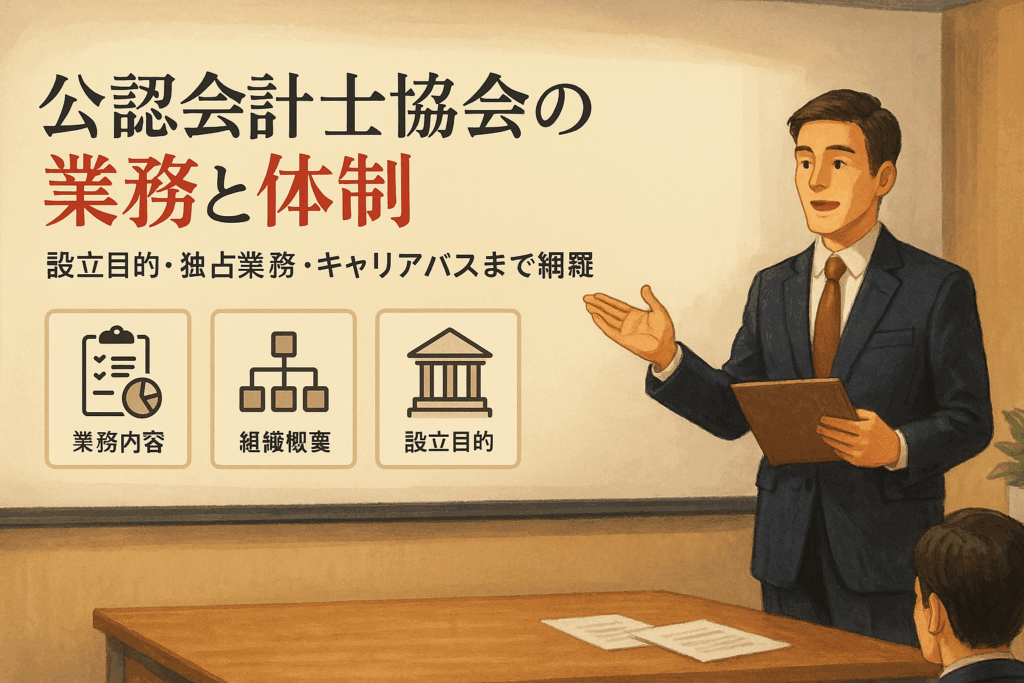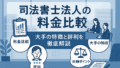日本の公認会計士協会は、【1949年】の設立以来、約【3.7万人】の会員が在籍し、全国13の地域会・43支部を擁する日本最大規模の会計専門家団体です。会計士というと“監査”や“試験の難しさ”ばかりが注目されがちですが、実は監査証明業務だけでなく、税理士登録や経営コンサルティング、政府機関・金融分野など、活躍の場は多岐にわたります。
「公認会計士の資格を活かせるキャリアって、本当に幅広いの?」「最新の制度改正や研修は複雑そうで、自分に合った情報をどう見つければいい?」こんな悩みを抱えていませんか? 実務経験や会員登録制度、最新トピックスまでを一元的に学べる情報源は意外と少なく、放置すると時間や労力を無駄にしてしまうことも。
本記事では、公式データや実際の制度運用にもとづく正確な情報をわかりやすく解説します。最後まで読むことで、会員制度や監査法人との違い、準会員の特典から全国の支部・組織体制まで、複雑そうな協会の仕組みやキャリアの可能性が一目で整理できます。
これから公認会計士を目指す方も、資格を活かしたい方も、最新動向を知りたい方も、読み進めるうちに確かな道筋が見えてきます。
公認会計士協会とは―組織概要と設立目的の詳細解説
公認会計士協会の設立背景と基本理念
日本公認会計士協会は、会計士による監査業務の厳格な基準を維持し、企業や団体の財務情報の信頼性を確保することを目的として設立されました。主な理念として「公正な監査を通じて経済社会の健全な発展に寄与する」という使命があります。協会は監督官庁である金融庁の監督下に置かれ、公共性と職業倫理の徹底を重視しています。また、国際的な会計基準や監査基準にも積極的に対応しており、会員に対して最新の知見や教育を提供し、日本経済の安定や発展にも寄与しています。公認会計士の使命は、社会や市場の信頼性を高め、経営の健全性を支えることです。
組織構成と全国の地域会・支部体制
日本公認会計士協会は、本部と全国の地域会および支部で構成されています。本部が全体の方針決定と情報発信を担い、各地域会(東京会、近畿会、東海会など)はエリアごとに専門委員会やセミナー開催、会員サービスなどを担当しています。以下のテーブルで主な地域会と役割をまとめます。
| 地域会 | 拠点 | 主な役割 | 会長(歴代の例) |
|---|---|---|---|
| 東京会 | 東京 | 会員サポート・研修 | 小倉、南 など |
| 近畿会 | 大阪 | 地域セミナー・監査指導 | 茂木、小倉 |
| 東海会 | 名古屋 | 業務相談・地域連携 | – |
| 北海道会 | 札幌 | 地域活動 | – |
会長は任期制で選出され、協会全体の責任者としてガバナンスを維持し、透明性のある運営を行っています。また、歴代会長や役員の情報は公式ページ内の一覧で閲覧が可能です。本部と地域会が連携し、会員一人ひとりの専門性強化や社会への貢献をサポートしています。
会員数の推移と準会員制度の仕組み
公認会計士協会には、正会員・準会員・名誉会員などの区分があり、会員数は年々増加傾向にあります。特に近年は会計士試験の合格者拡大や、若い世代からの入会が続いています。準会員制度は、試験に合格し実務経験を積んでいるが、まだ登録手続きを終えていない段階の方に適用される仕組みです。
-
正会員:公認会計士として登録済みの会員
-
準会員:試験合格者で実務経験中もしくは登録手続き中の会員
-
名誉会員:長年の貢献者等に与えられる称号
継続的な会員登録状況と準会員の特性
協会では毎年新たな会員登録や継続手続きが行われ、年度ごとの登録状況が公式に公開されています。準会員は、一定期間の実務経験やCPD(継続的専門研修)修了後に正会員へと登録が可能になります。準会員の期間は努力義務が課されており、講習参加やeラーニング利用などを通じてスキルアップが求められます。協会としても、準会員のキャリア形成や資格取得サポートに力を入れており、資格取得から実務まで一貫したサポート体制が強みです。
年度ごとの正会員・準会員数や新規採用情報も公表されており、会員総数は数万人規模に達しています。協会の活動は、監査法人、会計事務所、企業経理部門など幅広い分野の専門家を支えています。
公認会計士協会の独占業務と法的根拠
独占業務の範囲と監査証明業務の重要性
公認会計士協会に所属する会計士は、財務書類の監査や内容証明業務を独占的に担っています。監査法人や金融機関、上場会社といった組織も、社外の信頼確保のため公認会計士の監査証明を必要としています。
この独占業務は、会社の財務情報が正確かつ透明であることを保証し、投資家や社会の安心を支える重要な役割を果たしています。
下記のテーブルにて独占業務の主な範囲を整理します。
| 主な独占業務 | 社会的意義 |
|---|---|
| 財務諸表監査 | 投資家や債権者の判断材料となる信頼性向上 |
| 会計監査証明書の発行 | 会社や公益法人の経営透明性確保 |
| 年金基金の監査 | 年金運用の適正性を保証し加入者を守る |
| 内容証明書類の作成業務 | 証明書類の正確性による取引リスク低減 |
監査証明業務は社会インフラとして不可欠であり、協会が果たす公益性は非常に高いと言えます。
法令に基づく公認会計士協会の監督と登録事務
公認会計士協会は、法律に基づいて会員の登録や監査人名簿の管理、監督体制の整備を行っています。
登録手続きは厳格で、公認会計士になるには試験合格後に協会への登録が必要です。協会は登録内容や会員情報を適切に管理し、会員が監査法人や企業、金融関係機関などで業務を行う基盤を支えています。
協会の主要な監督・登録事務には以下のようなものがあります。
-
公認会計士の新規登録と変更・抹消手続き
-
監査人名簿および登録番号の管理
-
会員の業務状況や就職先、転職などの情報更新
-
法令遵守の監督と指導
-
地域会(近畿会、東京会など)との連携による管理体制強化
協会全体で会員を支え、業界全体の信頼性を確保しています。
自主規制機関としての役割と規律維持の対応
公認会計士協会は、単なる会員組織ではなく、高い倫理と規律を求める自主規制機関としての責務を担っています。
会員による監査不備や不正の発生を未然に防ぐため、協会は厳格な倫理規定・罰則規定を設け、処分や改善勧告を迅速かつ透明に行っています。
処分事例や規則変更点などは、会員向けポータル(JICPAマイページやCPDオンライン)・メールボックス・会報で周知されます。
主な規律維持のポイントをリストとしてまとめます。
-
倫理教育やCPD(継続的専門研修)の義務化で知識や責任感を強化
-
監査業務における違反には厳正な処分実施
-
規則や方針変更内容を全会員に対して迅速に公開
-
会員からの相談窓口や内部通報制度で透明性を維持
このように協会は専門職団体として、健全性と信頼性を守る規律維持の体制を徹底しています。
公認会計士協会の業務内容と資格活用の多様なキャリアパス
公認会計士協会は、会計士の質の維持向上、監査基準の策定、会員間ネットワークの強化など多岐にわたる業務を担っています。協会本部や各地域会(東京会・近畿会など)が連携し、全国の会員向けに支援体制を整備しています。会員専用のログインサービスやCPD(継続的専門研修)制度を導入し、監査法人や会計事務所、企業内の多様なキャリアを持つ会員の活動基盤を支えています。
監査業務の詳細と法定監査・任意監査の違い
公認会計士による監査業務は上場企業をはじめとする多くの法人の信頼性向上に貢献しています。その監査は主に法定監査と任意監査に区分されます。
| 監査の種類 | 主な対象 | 効力と特徴 |
|---|---|---|
| 法定監査 | 上場企業・大企業 | 金融商品取引法・会社法等に基づき必須 |
| 任意監査 | 中小企業・学校法人等 | 任意で実施される、目的や範囲も様々 |
法定監査は厳格な基準を満たす必要があり、社会的責任が高い点が特徴です。
一方で任意監査は企業の経営透明性や株主・取引先への信頼確保、資金調達時のエビデンスとして活用されています。
上場企業の法定監査と企業の任意監査の役割分担
上場企業では会計監査人として大手監査法人が監査を担い、金融機関や株主への信頼性証明が不可欠です。中小企業や団体では公認会計士の任意監査が経営状況のチェックやガバナンス強化に役立っています。それぞれの監査の役割分担を明確に理解しておくことは、企業の財務健全性向上に直結します。
税理士登録と会計コンサルティング業務の展開
公認会計士は所定手続きを経て税理士登録が可能となり、税務申告や税務相談にも積極的に従事しています。さらに、会計コンサルティング分野では、財務戦略立案や決算業務効率化、内部統制構築など多様なソリューション提供が求められています。
主な会計コンサルティング領域の例
-
決算早期化プロジェクト策定
-
中期事業計画の策定支援
-
法人税申告のアドバイス
公認会計士の専門知識と現場経験は、税務と経営アドバイザリーの両面で大いに活用されています。
税務対応や経営コンサルティングを担う公認会計士の業務幅
税務代理や相談対応に加え、経営改善・事業承継支援・資金調達サポートなど、会計士の役割は拡大しています。特に中小企業経営者が抱える課題解決において、公認会計士はビジネスのパートナーとして幅広く活躍しています。
-
税務調査対応
-
経営計画の作成支援
-
事業再生・M&Aアドバイザリー
上記のような多様な業務を通じて、公認会計士は信頼される専門家として期待されています。
企業内ファイナンス、FAS等専門分野での活躍
近年、企業財務や金融機関、官公庁へ転身する公認会計士も増えています。企業内会計士やファイナンシャルアドバイザリー(FAS)部門でのキャリアは多彩です。
| 主な活躍分野 | 仕事内容 |
|---|---|
| 企業財務・経理 | 上場企業の管理会計・連結決算・資金戦略等 |
| FAS | M&A財務DD、企業価値評価、組織再編支援 |
| 金融機関・官公庁 | リスク管理、金融商品評価、監督行政、調査業務等 |
幅広い専門知識と実践経験を生かし、社会や経済の発展を支える重要な役割を担っています。公認会計士協会は各分野のキャリア形成や専門研修を積極的にサポートしています。
企業財務や金融機関、官公庁での業務例と専門領域
企業では財務・経理部門のマネージャーやCFO、FAS業界ではM&Aアドバイザーや評価専門家としての需要が高まっています。官公庁や金融庁など公的機関でも、モニタリング・規制強化や政策立案の場面で公認会計士の知見が活かされています。
-
資金調達スキームの構築
-
企業価値向上のための経営指導
-
法規制対応や内部統制システム設計
このように公認会計士資格の活用範囲は極めて広く、高度な専門職としてキャリアの可能性が広がっています。
公認会計士協会の会員制度・会費・サービス内容の全貌
会員資格・準会員の違いと登録プロセス
公認会計士協会では、会員と準会員という2つの主要なステータスが設定されています。会員は、公認会計士試験の合格と登録を完了した者が対象です。一方、準会員は試験には合格したものの、実務経験など一定の要件が未達で登録手続きを進めている段階の方を指します。
下記の表は、会員と準会員の主な違いおよび登録プロセスの流れをまとめたものです。
| 区分 | 資格要件 | 役割 | 登録プロセス |
|---|---|---|---|
| 会員 | 試験合格+要件充足 | 実務業務可 | 本部での登録・会費納付 |
| 準会員 | 試験合格 | 限定的業務 | 準会員登録・実務継続中 |
会費制度についても明確に規定されており、会員・準会員とも登録時や毎年の会費納付が必要です。会費は、協会活動やCPD実施の原資となっています。登録や会費納付にはオンライン申請やマイページを経由して手続きが可能で、利便性も向上しています。
会員向けの研修サービスとCPD・CPEの実施状況
日本公認会計士協会では、会員の資質向上や最新の会計基準・監査基準に対応するため、継続的な研修プログラム(CPD・CPE)を提供しています。これにより、会員は専門知識のアップデートや法改正への対応を着実に図ることができます。
研修は下記のような多様な形式で実施されます。
-
オンライン講座(CPD Online、eラーニング)
-
会場型や地域会主催セミナー
-
特別講演やケーススタディ研修
免除条件には、所定の年齢や特定事情による特例措置があり、会員の状況に応じて柔軟な対応が認められています。オンライン研修の普及により、地方会員や多忙な現役会員も効率よく学び続けることが可能になりました。CPDやCPEの履修状況はマイページにて一元管理でき、利便性が高まっています。
求人情報からキャリア支援までの包括的サポート
公認会計士協会は、会員のキャリアアップを支える体制も充実しています。求人情報の公開や会員向けの転職・就職相談、セミナー・説明会の開催を積極的に行っています。
会員・準会員が受けられる主なキャリアサポートは以下の通りです。
-
公認会計士協会公式HPでの求人情報検索・閲覧
-
就職・転職フェアやキャリアセミナーの開催
-
新卒・大学生や経験者向け相談窓口の設置
-
転職エージェント連携による求人紹介
協会のサポートにより、「日本公認会計士協会の就職難易度」や「新卒年収」「転職後年収」など会員が関心を持つ情報もタイムリーに発信されています。多様な働き方の実現と会員の将来設計支援を、協会全体で強力にバックアップしています。
公認会計士協会の情報発信と専門資料の活用法
公式資料・報告書・監査指針のダウンロードと活用
公認会計士協会では、監査実務に関わる多様な公式資料や専門的なガイドラインを提供しています。入手方法は協会公式サイトの「資料・報告書」ページからのダウンロードが一般的であり、監査指針や品質管理報告書、倫理規範などを誰でも参照可能です。専門資料を活用する際は、最新の改訂状況や適用範囲を必ずチェックしましょう。資料ごとに利用者向け注意点や改訂歴が記載されているため、比較表や年度別リストで情報管理がしやすくなっています。
| 資料名 | 主な内容例 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 監査指針 | 監査業務の具体的手順、指針 | 公式サイトよりDL |
| 品質管理報告書 | 品質管理体制や改善ポイント | 会員限定・サイトよりDL |
| 倫理規範 | 会計士の行動規範 | 一般公開・サイトDL |
ポイント
-
必ず公式な最新資料を参照する
-
適用範囲・対象業務を念入りに確認
-
必要に応じて各資料を比較・整理
動画マンガ・パンフレットなど教育ツールの利用案内
教育や普及活動の一環として、協会は動画マンガやパンフレット、Q&A集などを揃えています。特に初学者や大学生、資格取得を目指す方には、基礎から体系的に学べるコンテンツが最適です。動画マンガでは、監査業務の流れや公認会計士の役割を分かりやすく解説。パンフレットは試験制度やキャリアパス、各地域会のサポート情報まで網羅しています。
おすすめ活用法
-
公認会計士業務を視覚的に理解したい場合は動画マンガを視聴
-
試験や資格への疑問がある場合はパンフレットのQ&Aを活用
-
地域会(東京会、近畿会など)の独自ツールもチェック
主な教育ツール一覧
-
初学者向けガイドブック
-
最新パンフレット(PDF配布)
-
ウェブ動画・漫画コンテンツ
会員専用ポータル・ログイン機能と問い合わせの対応
協会の会員は、専用ポータルサイトへのログインにより多様なサービスを利用可能です。マイページ機能ではCPD(継続的専門研修)履歴やセミナー申込、各種手続き状況の確認が簡単にでき、メールボックス機能で公式通知や案内を個別に受信できます。会員情報の変更や各種証明書発行もオンラインで完結します。
問い合わせ窓口はウェブフォームや電話、メールで対応し、一般利用者と会員それぞれに専用のサポートがあります。よくある質問も掲載されているため、疑問点の迅速な解決が可能です。会員ログインや問い合わせ窓口は、常に最新の情報管理体制が整備され、安全性と利便性の両面から評価されています。
会員サービス活用例
-
CPD受講履歴・証明書のオンライン取得
-
会費や規定の確認・各種申請の電子化
-
問い合わせ履歴や回答の一元管理
| サービス内容 | 主な機能 | 特徴 |
|---|---|---|
| マイページ | 履歴・証明書・各種申請 | 24時間利用可能 |
| メールボックス | 公式通知・連絡 | 確実な情報伝達が可能 |
| オンライン問い合わせ | 質問・相談を迅速受付 | 専用サポート体制で安心対応 |
信頼性・利便性を両立した会員向けの機能が、業務の効率化と情報把握を強力にサポートします。
公認会計士協会における監査法人・法人会員と業務連携
監査法人の役割と通報窓口の仕組み
公認会計士協会は、日本の監査法人や法人会員と密接に連携し、企業の財務報告や内部統制の健全化を推進しています。監査法人は上場企業や金融機関などの財務諸表監査を実施し、経済社会全体の信頼性向上に寄与します。近年は監査品質のさらなる向上が求められ、協会が設置する「監査ホットライン」など通報窓口の存在が重要になっています。通報システムの利用により、法令違反や不正の早期発見・是正が可能となり、会員と社会双方の利益が守られています。
下記は主な通報手段および利用状況の一例です。
| 通報手段 | 対象範囲 | 特徴 |
|---|---|---|
| 監査ホットライン | 監査法人・個人会員 | 匿名での通報も可能、迅速な対応 |
| 内部通報窓口 | 法人組織内部 | 社内規程で保護、社外監査機関との連携 |
| オンライン通報フォーム | 全国会員 | 24時間対応、証拠も提出可能 |
強固な監査体制と法令遵守意識が、日本経済の信頼基盤を支えています。
税理士法人や他専門法人との連携と業務範囲
公認会計士協会は税理士法人や社会保険労務士法人など、他の専門士業団体との連携も強化しています。特に税理士法人とは、税務業務や会計監査の分野で協業が進んでおり、中小企業や個人事業主へのワンストップサービスが実現しています。この連携によって、企業経営者にとって重要な会計・税務・労務の課題を総合的にサポートできる体制が整っています。
業務範囲の一例をまとめます。
| 分類 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 会計監査 | 財務諸表監査・法定監査・任意監査 |
| 税務業務 | 法人税・所得税の申告代行、税務相談 |
| 労務相談 | 労働保険・社会保険の手続き、助成金申請など |
| 経営コンサル | 資金調達、事業承継、M&Aなど成長支援 |
多職種との協働で幅広いニーズに応え、企業の経済活動を根本から支えています。
事業会社・金融機関・官公庁との協働事例
大手上場企業から地域金融機関、官公庁まで、公認会計士協会とその会員はさまざまな現場に関与し、高度な専門サービスを提供しています。特に事業会社では内部統制評価やリスクマネジメント体制構築の支援、金融機関ではコンプライアンス態勢調査や金融庁対応が実績として豊富です。また、官公庁との連携では政策調査や補助金審査事務も行われています。
代表例は以下の通りです。
| 協働先 | 公認会計士の主な役割 |
|---|---|
| 上場企業 | 監査・内部統制評価・IFRS導入支援 |
| 地方銀行 | 財務諸表監査・ガバナンス体制構築 |
| 官公庁 | 補助金審査・政策リサーチ・公共事業監査 |
多様な事業環境で蓄積された知見と実績が、社会からの信頼向上とサービス品質の維持に直結しています。専門性と幅広い連携力によって、今後も会計・監査分野のリーダー的役割を担い続けます。
公認会計士協会の透明性と社会的評価に関する分析
協会の沿革と歴代会長の活躍
公認会計士協会は、昭和24年の設立以来、日本の会計士業界の健全な発展を支えてきました。設立当初から厳格な倫理規定や監査基準を整備し、国内外の信頼を築いています。歴代の会長は会員の代表としてガバナンス強化や国際会計基準の導入に尽力し、近年ではデジタル化推進やCPD(継続的専門研修)制度の充実などを牽引しています。協会組織の透明性向上と社会的責任を重視したリーダーシップは、業界全体の信頼醸成にも貢献しています。
| 歴代会長名 | 任期 | 主な功績 |
|---|---|---|
| 南典男 | 2020年- | ガバナンス強化、デジタル化推進 |
| 茂木哲也 | 2016-2020 | 国際基準導入、監査の質向上 |
| 小倉潤一 | 2012-2016 | 地域協会改革、CPD研修制度の見直し |
社会的評価・評判と財務状況の客観的分析
公認会計士協会は業界・社会の両面から高い評価を得ています。会員の年収水準は一般的に高く、安定した職業として人気があります。外部有識者や企業からも「信頼できる専門家集団」とみなされており、信頼度は非常に高い水準です。協会自体の財務状況も公開されており、健全な運営体制が確認できます。
| 項目 | 数値・内容 |
|---|---|
| 会員平均年収 | 約800万円~1,200万円 |
| 年度別会費 | 約38,000円~ |
| 協会の社会的評価 | 高い信頼性、専門性が広く評価されている |
| 求人状況 | 監査法人・一般企業ともに安定 |
リスト
-
会員数は全国で大規模
-
求人ニーズは高く、就職難易度も相応に高い
-
外部評価・評判ともに安定的
国内外の公認会計士団体との比較検討
日本の公認会計士協会は、米国や英国の勅許会計士協会に比べても高い透明性と厳格な制度運営で知られています。米国のAICPAや英国のICAEWは政府や独立機関からの監督が強く、各国の会計基準やCPD制度にも違いがあります。日本協会もグローバル対応を進めており、国際的な信用力を維持するため、基準の統一や最新トピックスへの対応を積極的に行っています。
| ポイント | 日本 | 米国(AICPA) | 英国(ICAEW) |
|---|---|---|---|
| 監査基準 | 国際会計基準対応 | US-GAAP | IFRS/UK-GAAP |
| 継続教育(CPD) | 充実 | 必須 | 必須 |
| 透明性 | 高い | 高い | 高い |
| 会員数 | 多い | 非常に多い | 多い |
このように各国の会計士協会は制度上の違いがありますが、日本公認会計士協会は高水準の専門性と透明性で会員・社会から強い信頼を得ています。
公認会計士協会の今後の展望と最新動向
最新ニュース・イベント・業界トピックスの紹介
現在、公認会計士協会は業界の発展に大きく貢献するニュースやイベントを定期的に実施しています。特に注目されているのは、日商簿記甲子園や全国規模の会計セミナーです。協会の公式サイトでは最新の取組や研究発表も随時掲載されており、会員だけでなく業界関係者にも有益な情報が提供されています。
新着情報や最新トピックスを把握するために、以下の点がポイントとなります。
-
全国の地域会で開催されるセミナーや講演会
-
会長や歴代会長による挨拶・施策発表
-
監査法人や事務所との連携による新サービス導入
また、協会のマイページからはCPD(継続的専門研修)オンライン受講や会員向け情報も発信されているため、会計士のスキルアップにも活用されています。
| 最新ニュース・イベント一覧 | 概要 |
|---|---|
| 日商簿記甲子園 | 若手会計士・学生を対象とした会計知識向上大会 |
| 公認会計士協会研究発表 | 監査手法、財務会計、最新IT導入などの研究成果発表 |
| 地域会主催セミナー | 全国各地で行われる業界トレンドや制度改正の情報提供 |
国際基準対応とコンバージェンスの進展状況
公認会計士協会は国際会計基準(IFRS)への積極的な対応を進めており、外国公認会計士との橋渡しにも注力しています。グローバルな監査環境に合わせ、監査法人や上場会社と連携し国際基準への移行を加速。特に、監査報告書や財務諸表の開示内容では世界標準に則った透明性の確保が進められています。
公認会計士協会が推進する主な国際対応は次の通りです。
-
IFRSや国際監査基準への調和取組の強化
-
外国会計士受け入れ・資格認証の明確化
-
国際会計士連合会(IFAC)や海外団体との協力体制の拡充
| 国際対応の主なポイント | 内容 |
|---|---|
| 国際会計基準(IFRS)適用拡大 | 日本基準と国際基準のコンバージェンス(調和)が進展 |
| 外国資格者への認証支援 | 国を超えた会計専門家同士の認証制度が推進されている |
| グローバル協調の事例 | 多国籍監査法人との協力、国際会議への積極参加 |
法改正の影響と継続的な制度改善の方向性
近年の法令改正や新制度の導入により、公認会計士協会は積極的な制度改善と実務対応を続けています。たとえば会員制度の見直しやCPD義務化、透明な監査基準の整備などが挙げられます。こうした変化は監査法人や会計事務所の運営にも大きな影響を与えており、会員向けのガイドラインやFAQが随時提供されています。
今後の制度改善の方向性には以下の特徴があります。
-
会員登録・更新手続きの簡素化とデジタル化の推進
-
新資格試験や実務研修制度の改訂強化
-
会員費・業務責任等に関する規定の見直しと透明化
| 制度改善・法改正の要点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 会員制度の刷新 | 登録・CPDオンライン化、責任範囲の明確化 |
| 試験・実務研修制度の見直し | 新カリキュラム導入や資格認証プロセスの厳格化 |
| 会費や業務責任の新ルール | 会費支払方法の多様化(クレジットカード等)と責任規定精緻化 |
このように、公認会計士協会は業界の最新動向と国際標準への対応、法改正への適応を通じて、会員と企業双方の将来を見据えた各種施策を今後も推進し続けていきます。